1月2日。聖なる禅の信仰地にて、新春祈祷法要が行われました。
そこでは、民衆に寄り添った新春法要。そして、伝説の「龍の牙」が御開帳されました。
福井県越前市深草、第一関太平山龍泉禅寺。
通常は「龍泉寺」という名で親しまれている、禅の偉人、通幻寂霊禅師を開祖として創建された曹洞宗のお寺です。
1月2日に、この龍泉寺で新春祈祷法要が行われ、私も実際に法要に参加をさせていただきましたので、その様子を記していこうと思います。
また、この新春法要の際に本来非公開の「龍の牙」といわれる宝物が御開帳されました。
後半は、この「龍の牙」の御開帳の様子と、この宝物にまつわる伝説由緒、そして龍の牙を取り巻く龍泉寺や通幻禅師周辺の伝説を深く掘り下げて行こうと思います。
太平山龍泉寺とは

今回お世話になった龍泉寺さんは、武生の寺町の西、深草にあります。寺町からは外れていて、府中の河濯川の向こう側にあるので、どうしてもメインの観光ルートの外になってしまいがちですが、この龍泉寺は武生の歴史を語るには絶対にはずせない場所なのです。
まず、その龍泉寺さんについて、どのようなお寺なのか、簡単に紹介したいと思います。
龍泉寺は正式に第一関太平山龍泉禅寺といい、応安元年(1368)に藤原義清(一説に平氏安野泰久)が建立し、通幻禅師を開祖とした、大本山総持寺の直末寺院である曹洞宗のお寺。
慶長の頃、本多富正公が府中入城(越前府中城)の時、本多家の菩提寺となり、現在でも本多一族の墓所があり、巨大な五輪塔や墓石が並んでいます。つまり、武生の歴史の主要地ということです。
「第一関」とは、総持寺や永平寺などに入るために必ず通る「第一の関所」の意味であるといい、禅の世界の正しい入口、聖地になるということです。
通幻寂霊禅師は、禅の世界では非常に有名で、伝説界隈でも「飴買い幽霊(子育て幽霊)伝説」などで有名な方です。
また、通幻禅師は禅の修行の教育はかなり厳しかったとされています。
通幻禅師はこの龍泉寺で入寂されました。龍泉寺境内に通幻禅師の墓があります。
龍泉寺さんについては、通幻禅師と併せて、また別の機会に詳しく書きたいと思いますが、ここが重要な場所というのはおわかりいただけたでしょうか。
ただ現在は、永平寺のようにガチガチの堅いお寺ではなく、庶民寄りの寺院という雰囲気で、気軽にお参りできる印象でした。
今回は、新春ご祈祷法要と龍の牙について紹介します。
それでは、その様子を見て行きましょう。
新春ご祈祷法要
法要の雰囲気と概要
まず、新春法要に参加するにあたっては、事前に予約が必要です。
11月後半から12月くらいに龍泉寺公式ホームページにおいてアナウンスされます。
内容としては「ご祈祷」となるので、厄除けや家内安全など他多くのご祈祷をお願いできます。
基本、檀家さんや関係者の方が法要に訪れていたようです。毎年50名ほど法要に参加されるそうで、当日も雪やコロナが心配されましたが、晴れになり、50名近くが参加されていたようです。
正直少し緊張していましたが、想像よりはるかに和やかなムードでした。もちろん法要は厳粛ですが、服装は皆さん自由だし、親子で来られてる方もいらっしゃるし、若い夫婦?もいらっしゃる。まさに老若男女の方がいました。
私のように全くの外部の者でも何の違和感もなく馴染めましたし、ご住職やお寺の方、檀家さんか関係者の方も、とてもやさしく接してくださって、色々教えてくださり、ありがたい限りです。
法要の様子
連日雨や雪が降り続いていましたが、当日の午前中から法要が終わってしばらくまで、久しぶりの雲一つない晴れの天気でした。まさに、今回の法要にふさわしい日です。
2022年新春法要が始まったのは1月2日13時からです。受付は12時から始まりました。
(年によっても日時が違う可能性があるので、予約時に知ることができます。)

写真右の白雲台という建物から入り、本堂へ行きます。
受付、法要は本堂で行われます。
法要に際して、参加者全員で般若心経を唱えます。
その後、経本をめくっていきます。

法要前の本堂です。
経本を持って行く必要はなく、写真の通りお寺の方ですべて用意してあります。
また法要はいきなり始まるわけではなく、始まる前に、ご住職から流れや動きなどの説明があります。
般若心経も、唱える部分はわかりやすくラミネートしてあって、ふりがなもふってあるので、般若心経の漢字を読めない人でも全く心配いりません。
なので、一度も参加したことがない人でも参加しやすい形となっています。
(一応心配な方は、ユーチューブに曹洞宗公式の般若心経の動画があるので、見てみるのもいいかもしれません。)
経本をめくった後は、参加者のご祈祷に入ります。
ご祈祷の後は、ご住職の法話に移ります。
今回私は法要に参加していましたので、法要中の写真は撮っていませんが、龍泉寺さんの公式ホームページに「1/2 新春祈祷法要」という題でその時の様子が載っています。
>>太平山龍泉寺公式HP:http://www.mitene.or.jp/~ryusenji/
その時に、例の「龍の牙」が御開帳されます。「龍の牙」は、法要が終わった後にじっくり見ることができます。
宝物「龍の牙」御開帳

本来は非公開の「龍の牙」。
黒と金であしらった、三つ葉葵が描かれている厨子に、龍の牙がおさめられています。
「火伏せの龍牙」と呼ばれ、読んで字のごとくの信仰をうけています。
法要の際には、上段に置かれています。法要が終わった後は、下の見やすいところに置かれて、参加者が順番に拝んでいきます。かなり間近で見ることができるので、一見の価値ありです。
この龍の牙は、南越前町にある夜叉が池の雄龍の牙とされ、伝説界隈ではかなりの宝物です。
龍の牙についての詳しい伝説や由緒、そしてなぜ龍泉寺にあるのかなど、記事後半に見ていきます。
法要後は和やかに
さて、法要が終わりましたら、白雲台の建物の方で参加者全員に「ぜんざい」がふるまわれました。座敷の広間があり、そちらで皆さん座って和やかにぜんざいをいただきました。

食リポするつもりはないのですが、入っている餅が甘くておいしかったです。
そのあと、法要の参加者に龍泉寺の御札が配られました。
龍泉寺の新春祈祷法要は、和やかに且つ厳粛に進められます。
私のように外部の者で初参加でも何の心配もいらずに参加することができました。
この後は、ついに「龍の牙」について詳しく見ていきます。
「龍の牙」の伝説由緒と考察
龍の牙の伝説

龍泉寺所蔵の「龍の牙」。この龍の牙は、先ほども少し書きましたが、南越前町夜叉が池の雄龍の牙であるという伝説が伝わっています。
ただこの龍の牙の記述があるのは、「夜叉が池の伝説」ではなく、越前市池の上の「弥平蛇池伝説」の方に記述があります。
夜叉が池については、私がかつて夜叉が池に訪れた際の記事と共に紹介していますので、そちらを見て頂けたらと思います。
今回は、池の上の「弥平蛇池」の伝説について簡単に紹介します。
この伝説は夜叉ヶ池関係の福井県側の伝説で、美濃国の夜叉が池の伝説の後の話となっております。
ただ実は、この龍の牙の「弥平蛇池」伝説には、2通りの話があります。一応どちらとも見て行きましょう。
|
弥平蛇池 パターン1 池の上の小西弥平という豪商が、ある年の大干ばつの時、「雨を降らせたら娘を与える」という高札を掲げ、夜叉丸という武士に自分の娘を与えることで雨を降らせるという誓約を交わした。雨が降り、弥平の三女が自ら犠牲の名乗りを上げ、夜叉丸と共に家の裏にある池に入って、蛇となった。夜叉丸は夜叉ヶ池の大蛇だった。その後、娘と夜叉丸は夜叉ヶ池へ行った。しかし、すでに本妻である美濃の娘がいたので、弥平の娘との間に争いが生じた。 参考:『越前若狭の伝説』『神山村誌』 |
|
弥平蛇池 パターン2 池の上の小西弥平が大干ばつの時、「雨を降らせたら娘を与える」という高札を掲げ、ある武士に自分の娘を与えることで雨を降らせるという誓約を交わした。雨が降り、弥平の三女が自ら犠牲の名乗りを上げ、武士と共に家の裏にある池に入って、蛇となった。あるとき池ノ上が火災に遭う。(パターン1と描写同じ)焼け死んだ蛇の牙は現今禅明院に預けてある。 参考:『越前若狭の伝説』『福井県南条郡誌』『神山村要覧』『福井県の伝説』 |
この2通りの伝説の違いを簡単にまとめます。
| パターン1 | パターン2 | |
| 龍の牙 | 夜叉が池の雄龍 | 弥平蛇池の雄龍 |
| 弥平の娘が夜叉が池に移った時系列 | 夜叉が池の雄龍が娶りに来て蛇となって移る | 弥平蛇池の雄龍が焼け死んだあとに移る |
| 同じなもの |
|
|
見てわかる通りこの2パターンの伝説、「弥平の娘を娶りに来たのが、夜叉ヶ池の蛇か、弥平蛇池の蛇か」だけの違いで、時系列もそれ関係でずれがありますが、それ以外の描写が全くと言っていいほど同じなのです。
今回の龍泉寺さんでは、「夜叉が池の雄龍の牙」と伝わっています。
神山村誌の流れを汲んでいるようです。
出版元を見てみましょう。
- 『神山村誌』は、神山西尋常高等小学校出版。
- 『神山村要覧』は、村役場出版。
- 『南条郡誌』は、南条郡教育会出版。
- 『福井県の伝説』は、福井県鯖江女子師範学校郷土研究部出版。
『神山村誌』が一番地域密着でしょうか。他は行政とか外部の研究者だったりします。
禅明院さんが今まで所蔵していた龍の牙。ある理由で龍泉寺さんに移動してきて、「夜叉ヶ池雄龍説」が伝わっているということは、村内で伝わっているのが「夜叉ヶ池雄龍説」で、行政外部の通説が「弥平蛇池の雄龍説」ということでしょうか。
伝説が何通りもあるというのは、伝承伝説界隈ではいつものことです。
そこで私がいつも思うのは、どちらが本当かや先かを考えるのは面白い。しかし、だからと言って「これはちがう」「こっちが本物だ」というのではなく、本当かどうかは別にして、どちらとも実際に伝わって来たものだから、どちらも正しく、どちらも伝え続けなければならないということです。
これが、歴史学や史実の研究なら白黒はっきりつけないとダメかもですが、伝承伝説とはやはり、この「違い」が醍醐味でもあり、面白いのです。
そして実際に弥平蛇池にも取材に行ったので、その様子を記録しています。
今回の龍の牙での考察は、龍泉寺さんに倣って「夜叉ヶ池の雄蛇」説で見て行きます。
では、なぜ禅明院から龍泉寺に移されたのか。どういう関係なのかを見て行きます。また併せて、そもそも龍の牙が禅明院で預かることになった経緯も見て行こうと思います。
龍泉寺と禅明院と龍の牙
弥平蛇池の伝説では「禅明院に龍の牙が所蔵されている」と記載されています。
では、なぜ今龍泉寺にあるのか。今からそれを記します。
|
・禅明院 引用:『福井県南条郡誌』 |
禅明院は龍泉寺の末寺だったのです。龍泉寺のご住職は隠居寺ともおっしゃっていました。
つまり、龍泉寺と禅明院は直接的な関係なのです。
今回の法要当日、禅明院の方もいらしていていました。
龍泉寺ご住職と禅明院の方のお二人に、龍の牙が移動した経緯を聞くことができました。
この龍の牙が移動してきた経緯としては、10年ほど前に大雪によって禅明院のお堂が崩れてしまったそうです。禅明院は檀家制ではなかったので、資金が集まらなかったことで再建はされませんでした。その経緯があって、禅明院の宝物や建物の一部が龍泉寺へやってきたということです。
その中の一つが、「龍の牙」でした。他にも欄間の一部なども移動してきて、龍泉寺の白雲台の中に置かれています。
現在、禅明院のあった場所には石碑が建っているそうです。弥平蛇池と一緒にこちらも見に行かなくてはいけないですね。
そんなわけで、先ほどの蛇池の記事内で禅明院の跡も見に行ってきました。
では、なぜそもそも「龍の牙」を禅明院で預かることになったのでしょう。理由までは書いていないのでわかりませんが、経緯は書かれていました。
『福井県南条郡誌』によると、弥平の子孫が代々この牙を持っていたようです。そんな中、弥平の一女が村内の小西富右衛門に嫁いだ際にこの龍の牙を携えて行ったといわれています。しかし、この小西富右衛門の家は現在なくなってしまいました。そんな経緯があって、弥平の家から禅明院へ預けられたといいます。
さてなんとも偶然、と思います。しかし、これは偶然なんかではなく、今までの伝説を信じるとすれば、「運命」だったということがわかってきたのです。
さて、ここからは少しロマンある考察になります。これらの経緯が「運命」だということを導き出していきます。
「龍の牙」を取り巻く運命。通幻禅師と竜女救済伝説
今回、龍泉寺で御開帳された「龍の牙」ですが、弥平の家から禅明院へ渡り、現在は龍泉寺に所蔵されています。
これは、もしかしたら成るべくして成った結果なのかもしれません。
それを知るには、今回法要が行われた龍泉寺界隈の事を少し知る必要があります。
だいぶ冒頭で少し記載しました、「通幻寂霊禅師」そして「禅」と「通幻十哲」です。
この通幻禅師、実は「飴買い幽霊(子育て幽霊)伝説」以外にも、禅師自身の偉業伝説が多く残っており、その一つが女人救済、竜女救済伝説です。
竜女というのは、今どきのカルチャーにあるような「めちゃくちゃ美女」というイメージではなく、『近世仏教説話の研究 : 唱導と文芸』という書の言葉を借りるなら、「蛇身の妬婦」というイメージです。
武生周辺で代表的なのが、「白鬼女救済伝説」です。今の鯖江市に白鬼女橋という橋があります。その辺りが白鬼女伝説の地とされます。
通幻禅師が日野川ほとりで坐禅をしていると、恨みをのんで入水した妬婦の鬼女が現れ、禅師に救いを願ったといいます。禅師はその鬼女を成仏させました。
(ちなみに、この白鬼女ですが、『近世仏教説話の研究 : 唱導と文芸』内の一説に平泉寺時代に平泉寺の僧に恋をしてしまった60歳くらいの巫女さんが白蛇となったという話もあるそうです。天台宗ではありますが、安珍清姫伝説にしろそういう話が流行った時期なのでしょうか。)
また龍泉寺と同じ曹洞宗の大本山永平寺にも女人救済伝説があります。こちらは、道元禅師が永平寺を開くきっかけになったとされる話で、「血脈池の伝説」が挙げられます。
詳しくは、私が過去に実際に訪れた時の記事に書かれていますが、こちらも人ではなくなった女性を成仏させるという内容になっています。
このように曹洞宗では特に竜女や女人救済の話が多く見られます。
特に通幻派と呼ばれる通幻十哲からなる一派にはいくつも竜女に関する伝説があります。
その中で、通幻禅師の弟子通幻十哲の第六番目である「天真自性禅師」開祖の慈眼寺には、とても重要な話が伝わっています。
昔、嫉妬深い女がいて夜叉となった。その夜叉は四が谷の広野村があり、更に岩谷村がある。夜叉は昇って池に住み着いた。数百年住んでいた。天真自性禅師がやってきてその夜叉は解脱を得た。そのお礼に盆になると龍燈を捧げるという。そこを夜叉池という。
参考:『近世仏教説話の研究 : 唱導と文芸』内の『越前若狭地誌叢書』
わかりずらいですね。
もっとわかりやすく書かれているのが、今回訪れた龍泉寺ご住職執筆の『通幻寂霊禅師とその門流』という本です。
慈眼寺境内に龍神池というのがあるようで、そこにいた夜叉を天真自性禅師が成仏させて、夜叉は今の夜叉ヶ池に移り住んだといいます。法要の時は、その龍がお参りに来るので、必ず雨が降るのだとか。
参考:『通幻寂霊禅師とその門流』
本記事では、中身をかなりざっくりとしか説明していませんので、本にはもっと詳細に書かれています。
つまり、ここで夜叉ヶ池とつながってくるわけです。
ここで、「龍の牙」を思い出してみましょう。
龍の牙が、弥平の家から一女の嫁入りとして持ち出され、家はなくなり禅明院で預かるようになり、そして今、龍泉寺にある。なぜ龍泉寺にあるのか。
巡り巡った龍の牙と伝説は今…
通幻禅師が開祖として開いた龍泉寺。ここは、通幻禅師の入寂の地でもあります。
夜叉ヶ池の龍の牙。それは池の上の弥平宅を守って焼け死んだ亡骸です。
土地も違えば、関りすら感じられないように見えるこの2つの地。しかし、この2つはつながっていたのです。
竜女、女人救済の説話を知らしめる通幻禅師と通幻十哲の通幻派。通幻禅師自身の伝説から、それを継承するかのように天真自性禅師による夜叉ヶ池の夜叉救済。
そして、夜叉ヶ池に嫁いだ弥平の娘。その娘は本妻と妬み相争い、そして制した。まさに竜女女人救済の対象とされる「蛇身の妬婦」。
その弥平の娘の実家を守るために焼け死んだ夜叉ヶ池の大蛇。
その亡骸である「牙」は、弥平の家で保管され、一女が嫁入りに携え、そして禅明院へ。
なぜ、他の寺ではなく、禅明院なのか。先ほど「経緯はわかっても理由は分からない」と記しましたが、なんとなくわかりましたね。
通幻禅師開祖龍泉寺の末寺であるからです。
夜叉や龍、竜女、女人救済の通幻派のお寺だからです。
夜叉ヶ池の龍もその妻も、「龍の牙」という形になって、通幻派・通幻禅師を頼って再びやってきたのです。
そして今、禅明院から通幻禅師開祖入寂の龍泉寺へとやって来ました。
禅明院が崩れてしまったのは残念ですが、その際に龍の牙が龍泉寺へやってきたのは、単に末寺と本山という関係だからではないのでしょう。
事実上はそうなっているのでしょうが、その奥底には、龍の牙が「禅明院がない今、通幻禅師のいる龍泉寺でなければいけない」という運命によって、決まっていたのかもしれません。
そう考えると、龍泉寺の龍の牙がさらに特別なものに思えてきます。
禅と伝説の聖地は、庶民へと伝えられる時代に
武生の町、初詣の参拝客で賑わいを見せる京町から一つ川を隔てた場所にひっそりたたずむ大きなお寺、龍泉寺。
通幻禅師と禅の聖地としての顔、府中本多家菩提寺としての顔、夜叉龍救済を伝える伝承伝説としての顔を持ち、その数々の歴史文化伝説を静かに伝えています。
時代は流れ、聖なる土地でありながら現代、私たち庶民にもその地に伝わる多くの歴史文化伝承伝説を知ることができるようになり、和やかながらも厳粛に執り行われる法要は庶民の心のよりどころ。
皆から拝められている「龍の牙」自身も、ひょっとするとその龍泉寺の法要を救済として、心のよりどころとしているのかもしれません。
取材協力:『第一関太平山龍泉禅寺』『禅明院』
参考文献:『通幻寂霊禅師とその門流』『越前若狭の伝説』『神山村誌』『福井県南条郡誌』『神山村要覧』『福井県の伝説』『近世仏教説話の研究 : 唱導と文芸』『通幻禅師と龍泉寺』
【関連記事】
池ノ上の弥平蛇池伝説と今も残る遺産 ~禅明院跡・龍の牙・小西家【越前市】
基本情報(アクセス、最寄り駅バス停、駐車場)
最寄り駅は、JR武生駅。
バスに乗り換えると、昭和町バス停で下車、徒歩2分。
駅から徒歩だと、15分。
自動車では、武生ICから車で8分。
駐車場はあります。
龍泉寺公式ホームページ:http://www.mitene.or.jp/~ryusenji/


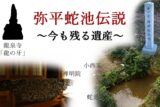



コメント