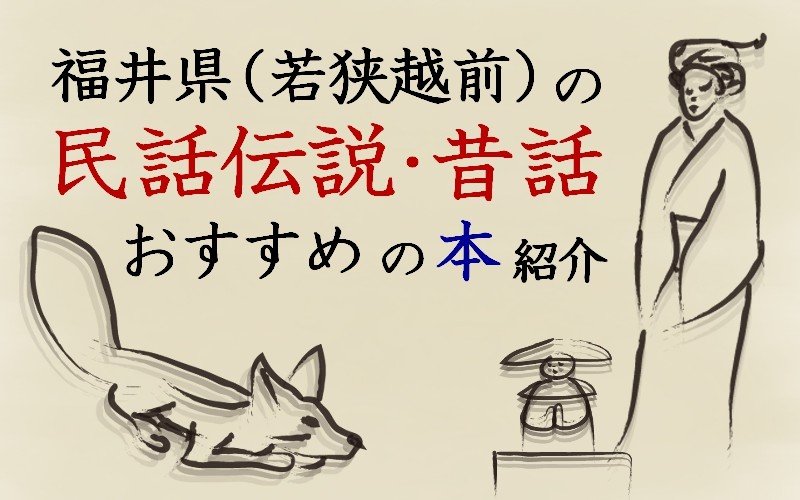
ここでは、「福井県の伝説・民話・昔話」稀に北陸全域の民話が載った本を紹介します。
私は普段郷土史などを見ていますが、非売品なので図書館じゃないと見れません。しかし、そんな郷土史並みに民話が集録されている市販本が意外にもいくつもありました。しかも、郷土史を書いている人が出している市販の本もあるのです。
むしろ、民話伝説を知りたいなら、今回紹介する本の方が伝説メインなので、郷土誌よりもわかりやすいかもしれないです。
では、私が知る限りの伝説民話集、民俗文化の市販本を紹介します。
- 本ごとにどんな本なのか特徴や中身の説明を書いていきます。
- 本の内容に関しては間違いなくお伝えしますが、思っていたものと違うとなっても責任は負いかねますので、購入の際は慎重に。
[日本の伝説 北陸]
新潟県から福井県までの伝説が39件掲載されています。
そのうち福井県は4件。
福井の伝説は、
- 嫁おどし肉付き面
- 東尋坊
- 八百比丘尼
- 二月堂修法の若狭水
が載っています。
内容は、所々に絵図が掲載されており、物語形式で進んだり、会話形式、説明形式で進んだりするものもあります。伝説の内容は非常に細かいです。
そして伝説の後には、細かい説明や時代背景、所々に原文、他の似類の話との比較などがなされており、考察もしっかりしています。
八百比丘尼に至っては、日本各地のみならず、海外の人魚伝説などとも合わせて考察されており、それに伴う絵も一緒に載っていて、違いも分かってかなり良い内容です。
良い点
伝説について背景や派生、元話も記載があるので、本当に研究並みの情報が欲しい場合この本は有効かと思います。話の数は少ないですが、どの伝説掲載本よりも深堀され検証されているので、この本に掲載されている伝説を知りたければ、この本で該当伝説はほとんど研究の域かと。
ちなみに[日本の伝説]は、北陸以外にも日本全域各地ごとに取り上げています。
東北や四国九州、東京まだまだありますので、調べてみてください。
[若狭・越前の民話 第1集][若狭・越前の民話 第2集]
杉原丈夫氏が書いている本です。
この方は、私が普段参考にしている郷土史の方の伝説も書かれている方で、福井の民俗研究家であり教授です。かなり本格的です。
嶺南54件、嶺北54件の合計108件の伝説が掲載。
目次で嶺南嶺北わかれています。
冒頭には手書きの地図があり、伝説の配置がだいたい見てとれます。
ページ数が多く、かなりボリュームがあります。
所々に挿絵が載せられ、伝説は淡々と載せられています。本当に「伝説集」です。説明は特段ありません。
内容は、「若桜のお水送り」などの伝統行事から、「はちすけ稲荷」「怪力シイ」「武周が池」「鼻欠け地蔵」など郷土史の方でも書かれている有名な伝説や、あまり有名ではない小話まで幅広く載せられています。
良い点
とにかく話が多いので、福井県の伝説を数でこなしたいという方におすすめです。また、深堀は後でやるから、とにかくどんな話があるか知りたい。という方にもこの本がいいと思います。
ちなみに、2冊目も発刊されており、こちらも多くの伝説が載っています。
こんな伝説が2冊も分けられて発刊されているので、凄い量です。
郷土史が見れない方は、これを見ておけば大体の福井の伝説は網羅できるんじゃないかと思います。
[福井県の民話]
挿絵付きの民話集です。
嶺北嶺南の福井県全域の民話30話が集められています。
目次に民話の舞台となる市町村が記載されており、東尋坊や機織りなどの有名な伝説が多めです。
この本の特徴は、最後の方にかなり詳しく記された地図が載っていることです。
さらに、民話で出てきた舞台の地や実際に伝わるもの(例えば「肉付き面」)の解説と写真が載っていたり、その地の説明、歴史、民俗文化などが解説されています。若狭の由来なども載っています。
こういったところが地元密着で、深く知ることができておもしろい所です。
良い点
福井の民話を知ることができます。前の『若狭・越前の民話』とは違い、簡易的に伝説を集めたい人におすすめです。
[福井のむかし話]
嶺南嶺北63話掲載。
挿絵付きで地図付きです。
坂井市の「おはるぎつね」の伝説や、まんが日本昔話でも登場した敦賀の「たいこときつね」など有名な話で舞台がはっきりとしている話もあれば、「the昔話」のような、どこの話なのか、いまいちわからないような話も掲載されています。
もちろん、現地に今も残る話もあるので、一つの引き出しとして良い本かとは思います。
地図は最後に載っています。結構詳細な位置が載っていました。
良い点
タイトルの通り昔話なので、前の『若狭・越前の民話』などの少しお堅いイメージとは違い、昔話の緩い感覚で読み進めることができます。子供でも分かりやすいと思います。
[若狭あどうがたり集成]
「若狭」と書いてありますが、敦賀から高浜までの嶺南地方の伝説言い伝え集です。
全135話。
2022年3月31日に発刊されたかなり新しいものです。
過去の郷土史や昔話民話集の本、そして各地に取材に行った時に地元民から聞いた話を編集しているそうで、なかなかの内容です。そして、この本の最大の特徴は、近代の話まで載っていることにあります。というのも、驚いたことに昔話だけでなく「タクシー」の話や「小浜線」の話まであるのです。しかも、民話的内容です。一部簡単に紹介すると
【小浜線の偽汽車】という題で、
「狐が汽車に化けて人を轢いた」
「東洋紡の引込み線で狐に化かされて轢かれた」
といった内容があるのです。
これは、当時列車にひかれる事故が多発していたことを意味し、それを昔話の「狐に化かされた」という内容に当てはめたという、昔話と近代の調和がなされた大変面白い内容です。民間の事故や歴史をも感じることのできる本なのです。
もちろん、他にも「人身供養」「天狗」などの伝説らしい伝説もあります。
その他は私が今まで見てきたような、有名な伝説は少ない印象でした。どちらかというと掘り出し物感があります。新鮮な内容です。
良い点
完全に嶺南特化型なので、嶺南地方の伝説・民話・言い伝えなどを調べている方は重宝するでしょう。嶺南に住んでいる方で地元のことが知りたい方・気になっている方にも良いものと思います。
[山の怪異大事典]
これは福井県や北陸だけではなく、全国を取り上げていますが、山に限定した怪異の特集ということでなかなか面白いです。
前397ページ(目次など併せて)
北海道・東北、中部、近畿などエリアごとにカテゴリー分けされており、そこからさらに都道府県ごとにまとめられて紹介されています。伝説民話だけでなく、近代の怪談や、本当にあったような感じの書き方の物、さらに2ちゃんねるの書き込みを元につくられたものまで、やたらと守備範囲が広い書籍です。
都道府県別の話の数はバラバラで、福井県周辺で言うと
富山…14件、石川…3件、福井…3件、滋賀…6件
載っているという感じです。
代表的なので言うと、石川が白山の千蛇ヶ池の伝説が載っていて、滋賀は伊吹山のヤマタノオロチの伝説が載っていました。あと、飛行上人という興味のある伝説もありました。掘り出し物の伝説もありそうな予感です。
福井はというと…、トンネルの幽霊や2ちゃんの書き込みの話でした…。いやいいんですけどね。1つだけ伝説ありましたが、私の知らない伝説でした。
という具合に、やたら範囲が広いながらも、山のみに関する伝説民話怪談妖怪などが収録された一冊です。
良い点
これは福井を目的にするというより、日本全国の山に関する怖い話・あやしい話を楽しむようなものだと思います。なので、「実際に行ってみて」とかではなく、家で読んで怪談を楽しむみたいに読み進めると楽しいでしょう。
[日本怪異妖怪事典 中部]
本のタイトルの通り、中部地方の妖怪や怪異を取り上げています。かなりボリュームあります。
全480ページ。
2022/8/26発売。(結構最近です。)
「中部」とあるので、他の地域「近畿」や「関東」もあります。妖怪怪異といえども、本サイトで取り上げるような伝説ばかりです。
当サイトでもお世話になっている『福井県の伝説』からの出典もあったり、全く聞いたことのない書物からの出典もあったりと、おもしろいです。
「おおい町のつるべおとし」や「東尋坊」、「味真野の狐」などの伝説もあり、まさに妖怪怪異という感じです。好きな人はおもしろいと思います。石川富山も載っていますし、「近畿」もあれば滋賀や京都の方の地域も見れるので、気になる方はその辺りも見てもいいかもしれません。
良い点
『若狭・越前の民話』ほどではないものの、それにも載っていないような民話が載っていることもあるので、民話を集めていると役に立ちます。あと簡潔にまとめられていることが多いので、スムーズに読み進められます。
[若狭がたりII――わが「民俗」撰抄]
全224ページ
出版2021年11月
若狭大飯町出身の小説家「水上勉」の多くの著書を結集した、まとめ本のようなものです。
大飯町に若州一滴文庫という施設がありますが、その施設の設立者が水上勉氏です。この『若狭がたりII――わが「民俗」撰抄』はその水上勉氏が、故郷での出来事や言い伝え、それに関係した他地方の民俗などを記した著書の民俗関係の内容をその文のままにまとめた形となっています。
良い点
姥捨てやなかなかネットでは簡単に紹介できないような内容の話まであり、なによりも水上勉氏が実際に体験した葬送や災害の話が鮮明に書かれており、それらをまとめているので興味のある話を一冊で読みやすく編成されています。
終わりに
今後も福井の伝説が載っている本が発刊されたり見つけたらここに載せて行きたいと思います。
また、伝説関連本以外の福井県に関する本を手当たり次第に紹介する記事もあります。こちらは歴史や地理・観光などで福井を取り扱っている本群になります。

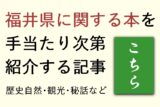


コメント