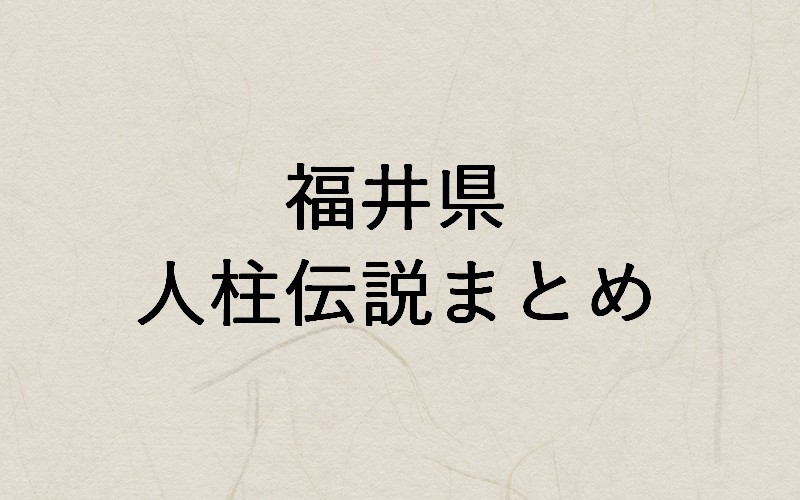
福井県には人柱伝説はいくつも存在しています。丸岡城や九十九橋など有名な伝説から、集落に伝わる人柱伝説まで存在します。
当サイトで紹介した人柱伝説はすべて、何らかの形で現地にその話を伝えるものが残っています。今回はそんな中から当サイトが取り上げた人柱伝説をまとめます。
丸岡城の人柱(お静)【坂井市丸岡町】
現存天守の丸岡城には有名な人柱伝説が伝わっています。
現地にもしっかりと祀られ、説明版まで置かれています。
『人柱お静』
福井の人柱伝説では一番有名な人柱ではないでしょうか。
| 人柱を必要とした理由 | 建設時に石垣が崩れたため。 |
| 人柱になった理由 | 我が子のため、もしくは弟のために人柱になった。 |
| 人柱の個人情報 | 丸岡近郊在住。二人の子供がいた(もしくは弟がいた)。享年38歳。 |
| 人柱になった年代 | 天正四年(1576)四月半ば。 |
その他、丸岡城には様々な伝説が伝わっています。人柱に関しても、男の人が人柱になったという伝説もあります。
お静は現在も天守近くに祀られており、人柱を身近に感じることができます。
詳細ページでは報告書なども交えながら伝説の内容に迫っていきます。
https://kofukuroman.com/maruokajo-hitobashira/
小浜城の人柱(組屋地蔵)【小浜市】
小浜城には長年忘れられていた人柱が存在します。
現在では地蔵尊が祀られており、説明版も設置されてその伝説を伝えています。
組屋地蔵の伝説は、地元の豪商である組屋家に関する伝説です。
| 人柱を必要とした理由 | 建設時に石垣が崩れたため。 |
| 人柱になった理由 | 人柱を連れてくるように命令を受けた父を助けるため娘自らが人柱となった。 |
| 人柱の個人情報 | 小浜の豪商組屋六郎左衛門の娘。 |
| 人柱になった年代 | 慶長六年(1601)あたり。 |
この人柱は供養されず、後に京極から酒井に城主が移った時に小浜城の蜘蛛手櫓で女の人が泣く声がするという話が城内に広まったことで、人柱の話が庶民から伝えられ、酒井の時代に奉り始めたと言います。ただそこから再び様々なことがあって、忘れ去られることとなります。
現在ではその蜘蛛手櫓の麓に組屋地蔵が祀られています。
組屋家のことも含めて、個別記事では詳細に記載しました。
https://kofukuroman.com/kumiyazizoh-hitobashira/
九十九橋の人柱【福井市】
福井市の中心地に足羽川が貫いていますが、その中心地の足羽川に架かる橋の中に九十九橋があります。
九十九橋が最初に架けられたのは柴田勝家時代とされ、その柴田勝家が、半石半木の橋を架けたのだそうです。
人柱伝説が起きたのは、その建設時です。
| 人柱を必要とした理由 | 橋建設時に柱が一本長さが足りなかったために期限が迫っていた。 |
| 人柱になった理由 | 我が子のため、人柱として橋の材料になる。 |
| 人柱の個人情報 | 石工勘助の母。 |
| 人柱になった年代 | 1575~1582年。 |
納期が遅れたら死刑になってしまう我が子のために、自らを犠牲にして橋の建設を助けたのでした。
それだけではありません。九十九橋の伝説にはもう一つ人柱の伝説が伝わっています。
荒木、駒屋の人柱伝説。こちらはそれぞれの家の娘が人柱になったという伝説です。
なぜ二つあるのか、それについても詳しく見ていきますが、これに関してはどうも年代が別の様なのです。
個別記事では、その伝説の内容と現地の様子、そして人柱の柱を探しています。
https://kofukuroman.com/tsukumobashi-hitobashira/
元覚堤の人柱(比丘尼塚)【永平寺町松岡町】
松岡付近にある九頭竜川から町を守る堤。その堤に人柱をたてたという伝説が残っています。
人柱を立てたのは、説が二つあり、建設時に立てた説と建設後しばらくして九頭竜川の氾濫で崩れてしまった後の再建時に人柱を立てた説があります。
| 人柱を必要とした理由 | 堤防が崩れないようにするために人柱を立てることとなった。 |
| 人柱になった理由 | 強制、または半強制。もしくは志願。 |
| 人柱の個人情報 | 旅の尼僧。 |
| 人柱になった年代 | 慶長六年(1601)ごろ(堤建設の時の場合)。決壊した後の再建時であれば慶長六年以降。 |
比丘尼塚は今はとある施設になっています。
元覚堤自体についても少し記しています。
詳しくは個別記事で。
https://kofukuroman.com/bikunizuka-hitobashira/
石盛の人柱(人橋地蔵)【福井市森田町石盛】
森田町に人橋地蔵という地蔵が住宅地内にある公園の敷地内に祀られています。
そこには説明版も設置されており、人柱の伝説を知ることができます。
二人の人柱がいます。
| 人柱を必要とした理由 | 大沼の橋建設が失敗するので、占いをしたら該当する旅人がくるということで、その旅人を人柱にすると橋の建設が成就するということになったから。 |
| 人柱になった理由 | 半強制。 |
| 人柱の個人情報 | ①母の菩提を弔うために京都へ向かう石丸という少年。奥州金丸長者の一子。十歳。 ②旅の僧。石丸と共に用途に向かう旅の共だった。 |
| 人柱になった年代 | 慶長あたり、1600年前後が濃厚。 |
占いによって人柱にされてしまった例です。
旅の僧は石丸だけは人柱にしないでやってくれと頼んだそうですが、石丸は自ら自分もなるといったという伝説があります。
そんな石丸がなぜ旅に出ることになったのかと現地の様子も個別記事に記載しています。
https://kofukuroman.com/hitobashizizoh-hitobashira/
領家の人柱(堤の相撲)【永平寺町領家】
領家の人柱は、人柱になった人の説が様々ありますが、今回は資料で語られた説を二つ見ていきました。
現地には地蔵が祀られており、「人柱」の文字も見ることができます。
| 人柱を必要とした理由 | 九頭竜川の堤が氾濫するので、村人が考えた結果人柱を立てて再建することにした。 |
| 人柱になった理由 | 強制。半強制。 |
| 人柱の個人情報 | 説①筬売り。 説②領家村人の若者。共通するのが相撲好きという点。 |
| 人柱になった年代 | 1789年(寛政元年)六月の決壊以降の盆16日。1789年(寛政元年)の盆か。 |
人柱が相撲好きだったということで、その人柱は埋められるときに、「此処で毎年相撲をしてほしい」と頼んだそう。それからは祭りとしてこの場所で相撲が行われてきたと言います。
現地の様子もじっくり見ていきます。
https://kofukuroman.com/tsutsumisumoh-hitobashira/
能登塩橋の人柱【福井市上東郷】
現地には人柱を供養するための地蔵尊と、伝説に登場する石碑などが祀られており、伝説そのものを現地で体感することができます。
| 人柱を必要とした理由 | 橋が何度やっても建設失敗した。偶然通りかかった塩売が「人柱をたてるとよい」といったので、人柱を立てることとなった。 |
| 人柱になった理由 | 塩売りが提案し、誰も人柱になりたくないというので、その塩売りを捕えて人柱にした。 |
| 人柱の個人情報 | 出身能登。塩売り。妻がいる。 |
| 人柱になった年代 | 永正16年(1519)、室町時代。朝倉氏の時代の説濃厚。 |
人柱をすすめた人が、捕らえられて人柱にされてしまう。そんな伝説です。
現地のお堂には、他にも石塔などもあり、この辺りにあった石造を集めたような場所となっています。
個別記事に現地の写真、伝説に登場する石碑も掲載しました。
https://kofukuroman.com/notoebashi-hitobashira/
今橋の人柱【敦賀市】
これほど平和な人柱伝説があるのかという人柱伝説。
人柱伝説なのに誰も犠牲にならないお話です。
| 人柱を必要とした理由 | 水害のたびに橋が流されるため。 |
| 人柱になった理由 | ー |
| 人柱の個人情報 | ー |
| 人柱になった年代 | 1635年以降。 |
この人柱は現在も見ることができます。
お寺に置かれているのですが、観光寺院ではないので、勝手に見ることは出来ません。
個別記事では許可を取って撮影した人柱の写真を載せています。
https://kofukuroman.com/imabashi-hitobashira/
人柱は今も残っている
人柱伝説は遠い昔に始まったようにも思えますが、歴史的にはそんなに古くない、結構詳細に伝わっているものまであります。それぞれの人がいて、それぞれの思いがあって、中には捕らえられて強制的に人柱になった人もいます。
そして年代はばらつきがあるようで、それなりにかたまっているようで…。
まだまだ人柱伝説は存在しています。
撮影が難しい場所や、何も残っていない場所など。しかしそこには確かに伝説が残っており、私が知らないだけで、本当は何か残っている可能性もあります。
福井県の人柱。これからも見つけ次第更新していけたらと思います。











コメント