福井県福井市に九十九橋という橋があります。かつて半木半石でかかっており、柴田勝家の亡霊伝説もあり心霊スポットとの噂も現代まで伝わります。
さらにもう一つ幽霊の話があります。それがこの九十九橋に伝わる人柱の霊ともされます。実際に柴田神社や安養寺、西光寺で人柱の柱や礎石であったとされる遺構を見て行きます。
人柱伝説
石工勘助の母の人柱
つくも橋
つくも(九十九)橋は、天正年間(1582ごろ)柴田勝家が築造したもので、北半分は木材、南半分は石材でできていた。このとき勝家は、石場(今の足羽山登り口一帯)の石工頭の勘助に石材四十八本の切り出しを命じ、もし期限までに納付しないときは、死罪に処すると申し渡した。ところが四十七本は切り出したが、残りの一本はどうしたことか寸法が短くて、柱に適しない。期限が迫り、勘助はただ死罪を待つのみであった。
彼には病気の母があった。彼女は勘助の悩んでいる様子を見ていった。自分にはかねて用意した石棺がある。その中へ生きながら自分を入れてくれ。この石棺を台にして柱を建てれば、寸法の不足を補うことができる。わたしは人柱になって橋を守ろう。勘助は泣きながら母の意に従った。この人柱は、水ぎわから西南二本目の柱であったという。
引用:『越前若狭の伝説』
九十九橋の人柱
北ノ庄の城主柴田勝家は、天正年間足羽川に石と木の架け分けの橋を造らせた。北半分は木材で、南半分は石材であった。之は戦国時代の事とてまさかの時には敵を渡らせない為に木材の方を落とすつもりであった。川の水は丁度北半分にしか流れなかったからである。さて此の時、石材を全部調達したのが勘助といふ石工の棟梁であった。彼は足羽山登り口(五獄楼下)に住んでいた。此の辺一帯を石場と呼ぶのは勘助などの石切場や石置場であった所を、俗に石場と呼んだのがいつしか地名となったのであるといふ。勘助は此の大きな仕事をいひつかって、万事手落のない様に懸命に働いたのだが、一つ大変こまったことは支柱となるべき石材が一本どうしても足りないことである。もう一本必要な長さの石を切り出すことが出来ない。つぎ足す事は許されない。勘助は非常に悲しみ案じているうちに期限は追々迫ってくる。がどうすることも出来ない。いよいよ明日といふ時、我が子の一大事を見るに見かねた母親は、美しくも悲壮な心を語った。「柱一本足りないために、お前の男は立たず命さへも案じられる。私はどうせ老ひ先短い命だから人柱となって大橋を守らう。幸平素から死んだら入るように石棺が造ってあるのだから、それを台に柱を立ててくれ、私の一心で必ずゆるぎはあるまいから。」と。勘助はどんなに苦しかったことだらう。然し公の大事にはかえられないので涙ながらに、母の棺を土台として川底の土深く生きながら埋もれた母の冥福を祈りつつ工事に専念した。南の方から数えて六本目の柱がそれであった。勝家は此の母親を相生町の西光寺(勝家の菩提寺)へ厚く葬った。相生町の岡西光寺ではこのような因縁で旧藩政時代のある頃まで、毎年月日を定めて河原に出て、この柱をめぐって供養の念仏を唱へたとも伝えられている。此の柱は享保十二年の地震には折れたため取換へられ、更に明治四十二年の大橋架替には石材の部分全部と共にこの柱も取除かれてしまった。現今は柴田神社に無盡燈として柱の姿のまま建築され、表に「福井大橋係柴田公創設以半杠半矼明治己酉改築因請縣廳移舊石柱作燈爲記念當社々掌福岡徳次郎謹書」裏に「享保十二年」と刻字の見えるのがそれである。
引用:『福井県の伝説』
大橋人柱の由来
足羽川大橋現今の九十九橋の起源は、柴田時代と記録されて居るが、同橋は当初より南の方は石、北の方は木といふ風に一種異様の構造を其の儘明治の末年まで伝へて、福井の一名物と称へられたことは世人の知る所である。而して石の方数多の橋の中に人柱と称して不思議の来歴を有した一本は、現今柴田神社境内の常夜燈となって居るそれであるが、来歴の大略は先づ斯様である。
柴田勝家が足羽川大橋を架設する際に柱とすべき石材の切出方を命ぜられたのは、石工勘助といふ者であった。然るに柱は四十八本といふ多数の上に、日限に狂ひの生じた場合は斬罪の刑に処するといふ厳重な申渡し、勘助に於ては昼夜兼行にて石材の切出しに就事したが、或は硬軟の差あり、或は亀裂の虞れありて漸く四十七本まで揃へたが、残り一本が少し短くして而も日限は其は翌日に迫って来た。
殆んど手を空うして死を待つの有様を病床から見た実母の某、予て自身の死んだ場合に用ひて呉れよと勘助に命じて置いた石棺に生きながら自身を納め、右の柱の下敷きとして埋めて呉れたならば、丁度其の長さに合ふのみならず、一心人柱となって此の急場を無難に切抜けやうと申し出した。勘助泣くなく実母の意に任せて、生きながら石棺と共に埋めて見ると、果せるかな他の四十七本と寸分の長短がないのみならず、無事に検分も済ませた。右の柱は水際より西南二本目であった。
さて、勘助の実母が生きながら人柱となった事が、それからそれへと自然に伝はり、柴田の菩提所なる岡西光寺(現今常磐木町)の檀徒が菩提のために常念仏をやったのが、今坂者に於ける祝儀等と同様のものとなり、旧藩時代には岡ソウドが来たと称して応分の志を取らせたものである。右人柱は享保年間二つに折れ、福井藩にて新たに取り替へられたもので、これ柴田神社境内の分に享保年号の刻せらるる所以である。猶笏谷其の他の石は山出しの儘なれば、如何なる天変地異にも折れずと伝へられ、足羽神社に角の荒削りの石鳥居があったが、其の後藩より外見面白からずとの理由で多少の角の方を削り落とした。
石工勘助の屋敷跡は昨今夢想で有名な足羽下町按摩朝倉次郎作の宅に当り、庭内には勘助信仰の弁才天の祠があったが、去る明治三十二年の橋南大火に焼失して以来は、其の跡草に埋められて居る。次郎作が夢想一天張りで騒がすとも、埋蔵物の皆無といふことは断言できないのであるから、一番住宅全部を壊して発掘を試みるも決して徒労ではあるまい。
引用:『福井藩史話 福井城の今昔 上巻』
『九十九橋ものがたり写真集』『福井むかしばなし』も同じく勘助の母が人柱になったという話です。
名前までしっかり残っており、その石工頭がどこに住んでいたかまで特定しているほど、しっかりとした伝承のようです。
様々な郷土史に記載されており、どうやら九十九橋の人柱伝説といえばこの伝説がメジャーなようです。
加えて、『九十九橋ものがたり写真集』は1986年発刊で、人柱の柱のその後の経緯を詳しく追っているのでかなり参考になります。後に紹介します。
西光寺さんに以前柴田勝家の伝説でお世話になったときに、人柱伝説についてもお聞きしました。
ただ、現在人柱についての伝説は伝わってはおらず、人柱供養についても伝わっていないとのことでした。
九十九橋が一番最初に建設されたのは、
『中日本建設コンサルタント株式会社 島田技術顧問のサイト F18 福井県』
https://www.nakanihon.co.jp/gijyutsu/Shimada/BridgeData/f18FI.pdf
によると、「1577‐3(1591?)」と書かれています。
1575~1577年ともされています。
柴田勝家が生きていた時代にできたということになると、1591年ではないと思います。
つまり、
- 人柱が起こったのは、1575~1577年あたり。
となる。ということです。
荒木、駒屋の人柱
九十九橋人柱の怨霊
福井藩の士の中で最も蛮勇を伝へられたのは俗にいふ毛矢士(けやざむらい)の一派で、すね者と奇行とで近辺で評判であった。或夜更け草木も眠る丑満の頃真黒の暗の中を酔っ払った毛矢士の一団が今しも九十九橋に差しかかった。もとより足羽川の兩岸には灯の影さへ一つ見えず暗い空からはポツリポツリと雨さへ落ちて来て、何となく気味の悪い夜であった。此の橋にさしかかったさすがの毛矢士もあたりの様子に酒の醉もどこへやら、腹の底からぞくぞく寒気が催しさう、只一団となって南の方へ歩んでいた。其の時先頭に立っていた一人が何やら物凄い奇声を挙げたかと思ふとその場にぶっ倒れてしまった。それっと一同は無我夢中後を見ずに逃げ戻ってしまった。橋の真中にとてもきれいな女が傘をさし、青白い焔を背に負うてニタリと笑ったその物凄さに思はず奇声を挙げて正気を失って倒れてしまったのであると後で分かった。こんな噂が藩中ににひろがるとそれからといふものは、我も我もとその正体を見届けてやろうと探検に出掛けたが誰も彼も橋の真中でぶっ倒れてしまふといふ有様であった。その頃町の人々の間にまた噂がたった。九十九橋は架替毎に橋畔にある荒木、駒屋の両家が渡り初めを式をするのが例となっているが、或る年の洪水に木橋のほうが流されたので工事にかかったが、工事半で何度も流失の厄にあった。それで両家から悪神の怒りを鎮める為に柱杭の下へ人間を生埋にしたから人柱の怨霊が出るのであると。こんなことで夜更けになると九十九橋を通る人がなかったといふ。
引用:『福井県の伝説』
さきほど、勘助と母の人柱伝説がメジャーだといいましたが、その他にも以上のような「荒木、駒屋」の人柱伝説も伝わっているようです。
これはよくある、「諸説ある」という伝説ではなさそうです。
なぜなら、注目してほしいのです。
「或る年の洪水に木橋のほうが流されたので工事にかかったが、工事半で何度も流失の厄にあった。それで両家から悪神の怒りを鎮める為に柱杭の下へ人間を生埋にしたから人柱の怨霊が出るのであると。」
つまり、橋はもうすでにできている時代、とある年、洪水で流されて修復工事の際に人柱にした。
これは完全な柴田勝家の「勘助と母」よりも後の時代の話なのです。
年代不明。九十九橋は江戸時代に何度も架け替えられています。
つまりこの九十九橋には、2つの人柱があるということです。荒木、駒屋両家という言い方が本当なら、2人の娘が人柱になっており、合計3人がこの九十九橋に人柱となったということになります。
絶望しないでください。
正直私も驚愕しました。一つの橋に少なくとも3人人柱になっているという伝説があると。
もちろんあくまで伝説ではあります。藩政時代の幽霊伝説はいくつかある中の一つの噂かもしれません。
それでも伝わっていることに価値を見出すなら、これは供養すべき3人の人柱を信じるほかありません。
九十九橋
さてそんな人柱の伝わる九十九橋へ行きましょう。

九十九橋には人柱伝説以外にも柴田勝家の亡霊伝説もあり、なかなか禍々しい伝承が複数伝わっているようです。
勘助と母の伝説では、『福井藩史話 福井城の今昔 上巻』『越前若狭の伝説』『福井むかしばなし』には水際から数えて西南二本目の柱であるとされています。
しかし、『福井県の伝説』「南の方から数えて六本目の柱がそれ」としています。
おそらく、これはどちらも同じ柱を意味しており、水際から数えるか、橋のたもとから数えるかの違いではないかと思います。

しかし、『九十九橋ものがたり写真集』を見てみると、何本目が人柱かというのにばらつきがあるようです。
水際から数えて二本目とか、南から数えて北方の何本目とか色々とあり、しかも四十八本すべて見た目が同じで、当時見物で来た人々にとっては見つけにくいものだったそうです。
それが確定したのは享保に入ってからで、享保十二年に福井地方の大地震で柱が折れ、それを修復したときに、上段に「享保十二年」という年号が彫られてから、これが他の四十七本と人柱の柱を区別する「決め手」となって、より一層人々の関心を集めるようになったと言います。

しかし先ほどの3人の人柱の話で言うと、人柱が何番目かにばらつきがあったというのは、ある意味人柱が複数人いたという裏付けになっているのではないでしょうか。
『九十九橋ものがたり写真集』では主に勘助と母の伝説しか取り上げていないので、確定しようとしていますが、北側、つまり木橋側。
木橋が流出したから人柱にした。ならば北側にも人柱があってもおかしくない。ということになりそうです。
現地には歴代の九十九橋の様子が描かれています。

ちなみに今も木橋石橋の雰囲気を味わえる場所があります。

柴田神社に木橋石橋が一部おかれているのです。
人柱の柱は今もある?
さて、まずは勘助と母の人柱です。
例によって『九十九橋ものがたり写真集』によると、明治四十二年に時代の流れで橋が架け替えられることになり、それと同時期に柴田神社も神苑が広がり、それを機に新たな神殿も建立しようとしていたといいます。
その時に、当時の初代神主が、人柱の石柱のことを「これこそ、わが柴田神社に最もゆかりの深いもの。九十九橋解体の際には、なんとしてでも、それを貰い受けねばならぬ」と決心し、神主他代表四名の信徒の名前で県へ下付願を出し、箸の解体の際に神社の境内に移したと言います。それで雅趣に富んだ常夜燈を作り上げ、その正面に「福井大橋、係柴田公創設、以半木半石名、明治己酉改築、因請県庁、移旧橋石柱、作灯為紀念」と刻んだといいます。
この当時は人柱の柱であるということは断っていなかったといいますが、柱の上段には「享保十二年」の刻印があり、柴田神社の名物となっていたようです。
伝説では享保十二年に取り替えられたとしていますが、『九十九橋ものがたり写真集』では取り替えられたというよりも、修理され、その時に架けられたそのまま「享保十二年」の文字が刻印され、その後明治時代に橋自体が架け替えられ、ここでようやく柴田神社にその人柱が来たという経緯であるということになっています。
しかし、現在もそのような柱があるのでしょうか。
九十九橋近くにも石柱がありますが、書かれている内容を見てもこれではなさそうです。

柴田神社にはいくつか九十九橋の石柱があります。しかしどれもこれもそのような文字は見当たりません。


『九十九橋ものがたり写真集』にはその理由が書かれていました。
しかしながら、この歴史ある「人柱の石柱」にも、とうとう運命の日がやってきた、昭和二十三年の大地震だ。
この大地震で、当の柴田神社が受けた被害も甚大なもので、鳥居や灯籠などの被害はいうに及ばず、神社の創建以来、石垣の上に建っていた、例の巨大な「柴田神社之碑」がぶっ倒れたのに続いて、この人柱の常夜灯も、真ん中から折れて、上半分が崩れ落ち、粉々になって、かの「享保十二年」の銘も、跡形もなくなってしまった。まことに惜しい限り、遺憾の極みという他なかった。
現在、柴田神社の拝殿の前に立って、左の方を眺めると、そこに古びた金くさりと、二本の石柱。一本は完全で一本は半壊れになった、二本の石柱を見る。
古いくさりは、勝家公が九頭竜川の舟橋に使用したもので、又石柱の、完全な方の一本は、有名な勝家公と、お市の方の、辞世の句を彫りこんだもので、古くから「ほととぎすの歌碑」として、市民に親しまれてきたもので、地震にも壊れなかったもの。そしてもう一本の方、半壊れになっているもの。そして正面に「柴田勝家公によって架けられた半木半石の名橋旧九十九橋の石柱と九寿龍川舟橋の鉄鎖である」と、説明文が彫りこまれているもの。これが実に、これまで述べてきた、この九十九橋「人柱の石柱」の、全く変わり果てた姿なのだ。
地震のとき、真っ二つに壊れて、例の大事な「刻銘」など、失ってしまった以上、もう値打ちがなくなったといって、残骸を地下に埋めようという声も、当時あったのだが、しかし、古い歴史を持った石物であり、しかも何百年もの間(たとえ伝説にしろ)多くの人によって、供養され続けてきた代物でもあるので、これに反対する信徒も多く、結局のところ再考、思案の末、現在見られるような「くさりがけ」くさりを乗せる「台」のようなものに変身、作り替えして、保存することになったものである。
引用:『九十九橋ものがたり写真集』
ただし、この『九十九橋ものがたり写真集』が発刊された時から柴田神社もだいぶ様変わりしています。
『九十九橋ものがたり写真集』にある柴田神社向かって左手の鎖置き場も今は資料館になっており、鎖はあるものの肝心の説明が刻まれているという石が見当たりません。

資料館の裏手に石がいくつか並んでいるところがあります。
その一つに、勝家とお市の辞世の句が刻まれている石柱がありました。

『九十九橋ものがたり写真集』でていた、人柱の石柱と2本あったうちの一つです。
ただその他には、笏谷石の柱は見当たらず、裏手にもありませんでした。
ネット上に昔の柴田神社の鎖置き場の写真が出てきました。
https://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/siryou/hen1/syou5/2kasen3.html
『九頭竜川流域誌』国土交通省近畿地方整備局 福井工事事務所
https://www.kurotatu-jinja.com/funabashi
『黒龍神社HP』(舟橋)
おそらく、『黒龍神社HP』(舟橋)の写真の左端にバッサリといったような石柱が立っているのですが、これなんじゃないかとも思われます。断定はできません。
では柴田神社にそれらしきものがあるかというと、2つそれらしきものがあります。
一つは屋外の九十九橋模型の横にある石柱。もう一つは資料館内の鎖の横に置いてあるもの。

鎖まであります。鎖場と縁の深い人柱の柱であるという点においては、関連性はあります。

そして屋外の方はまるで屋内の片割れかのような形状。
両方とも柱の長さにしては短く、折れた感じがします。
ただ気になるのは、どうもたもと辺りは短い柱が使われていたようでもあるのです。なので折れたから短いとは一概に言い切れないという所が正直なところです。
西光寺さんに西光寺さんの人柱供養に関して聞いた際に、西光寺さんは柴田神社とも縁があるからと、この件に関して柴田神社の方へ聞いてくださったのですが、やはり現在は人柱の話は伝わっていないとのことでした。
しかし、柴田神社の資料館の係の人に話を聞いたところ、とある話をお聞きすることが出来ました。
「柴田神社に人柱の遺構があるのは聞いたことないが、足羽山の麓にある安養寺というお寺に人柱の礎石があるというのは聞いたことがある」
というのです。
伝説も見ていても、たしかに柱の下に埋めた礎石のような役割を果たしていたようなことから、この話は興味があります。
人柱の石柱ではないですが、礎石があるということなので行って見ます。
人柱の礎石のある安養寺

人柱の礎石。それ則ち人柱そのものなのでは?と思いながら赴きました。
どれが例の礎石なのかわからなかったので情報を探すと、安養寺さんのホームページがあり、
http://www10.plala.or.jp/anyoji/index.html
「境内の様子」の項目に、「九十九橋の礎石」との題で写真が載っていました。
なのでそれと同じものを探した結果見つかりました。

これのようです。
結構普通の礎石に見えます。
さて、真意を確かめるべく安養寺さんにお聞きしました。
すると、『足羽昔ものがたり集』という郷土史に安養寺と人柱についての関わりの話が載っているとのことで、それを教えてくださいました。そしてその内容も教えていただきました。
誠にありがとうございました。
後日その資料の実物をじっくり見ました。その内容によると、
寺伝によれば柴田勝家公は半石半木の九十九橋をかけた際、橋柱の礎石の一つは当山檀徒総代であった駒屋家の娘を人柱に立てたもので、この橋の改修の折りに掘り起こされたものを菩提所である当山に寄進されたと伝わる。
引用:『足羽昔ものがたり集』
というものです。
この文を見ると、本当に人柱の礎石であるということです。
まさか人柱の上にあった柱の方ではなく、礎石の方を見ることになるとは驚きです。
しかもこの内容、「勘助と母」の伝説ではなく、「荒木、駒屋家の娘」の伝説の方であるということが注目するところです。
つまり、「勘助と母」の人柱も「荒木、駒屋家の娘」の人柱も、両方が現代、近年まで遺構が残っており伝わってきているということなのです。どちらか一方ではなく両方です。
これは素晴らしいことです。
伝わっていることに価値があるということをモットーにしている私にとっては、両方が話も現物でも伝わっていたというのはとも価値のあることだと思います。
それはつまり、やはり両方共が供養され、両方共が本当にあったかもしれない人柱伝説であるということになるのです。
人柱伝説を想い
人柱。それは悲しき伝説。
九十九橋の人柱は、子を想う母の、悲しくも愛のある話。そしておそらく総代の娘というだけで人柱にされてしまった悲しき話。
何人もの悲しき人柱たち。その伝説の上に架けられた福井を代表する名橋となった九十九橋は、今も人々や自動車が行きかう重要な道となっています。
今も昔も、この人柱たちは私たちを福井の中心から支えているのかもしれません。
それでも今はどうか、供養され、安らかにお休みになられていることを願わずにはいられません。
参考文献
『越前若狭の伝説』著者杉原丈夫 出版1970
『福井県の伝説』著者河合千秋 出版昭11
『福井藩史話 福井城の今昔 上巻』著者森恒救 出版1975.10
『九十九橋ものがたり写真集』著者新九十九橋名橋化促進会 出版1986.5
『福井むかしばなし』著者福井市教育委員会 出版1973.11
『足羽昔ものがたり集』著者足羽熟年友の会 出版1986
『九頭竜川流域誌』国土交通省近畿地方整備局 福井工事事務所
『黒龍神社HP』(舟橋)
中日本建設コンサルタント株式会社 島田技術顧問のサイト F18 福井県
協力
西光寺
安養寺
関連記事:『福井県の人柱伝説まとめ』
基本情報(アクセス)
九十九橋
| 最寄り駅 | 福井駅から徒歩17分 |
| 自動車 | 福井ICから13分 |
| 駐車場 | 橋北に有料駐車場有 |
柴田神社
| 最寄り駅 | 福井駅から徒歩7分 |
| 自動車 | 福井ICから7分 |
| 駐車場 | 線路の反対南側に駐車場有 |
安養寺
| 最寄り駅 | 足羽山公園口駅から徒歩11分 |
| 自動車 | 福井ICから13分 |
| 駐車場 | 有 |




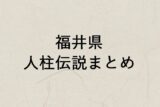


コメント