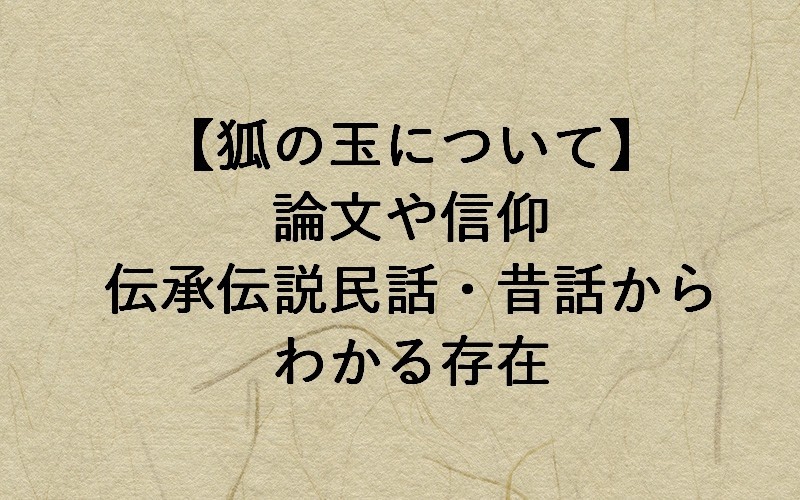
福井県には「狐の玉」の信仰があります。
狐の玉は信仰対象でもあり、伝承伝説でもあり、昔話でもあるという、かなりジャンルの幅が広い存在です。福井県以外にも狐の玉の信仰はありますが、今回は福井県を重点的に見て行こうと思います。
はじめに
狐の玉については、かなり情報が出てきています。
ネットで調べても、取材に行っている人や、民俗学者である金田久璋さんの新聞の記事が出てきており、狐の玉自体の写真も出ています。
金田久璋さんは若狭出身で、後に見る論文『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』や『あどうがたり』もこの方が書いていますが、狐の玉の話は特に若狭での話や研究対象になっているようです。
論文『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』は小浜市の若狭図書学習センターにあります。若狭の狐の玉については金田久璋さんの論文を見れば今わかっているだけは網羅できるほどです。気になる方は見てみてください。
なので今回は、狐の玉というジャンルの入り口になるような記事、また関係のあるような話などを取り上げて、狐の玉を総括したような、興味を持ってもらえるような記事にしていければと思います。
内容は薄いかもしれませんが、是非最後まで見て行ってください。
狐の玉の昔話や物語
昔話民話系
最も有名なのがおそらくネット上で一番最初に出てくる、『民話の部屋』というサイトの『狐の玉 – 福井県の昔話』の内容でしょう。
寺の小僧が狐の巣穴から狐の玉を盗んで、狐がこれを取り返し、更に小僧が稲荷明神に化けて狐の玉を再び盗み取るという話です。この話では狐の玉がないと狐は化けることができない。
という設定になっています。
その他にも『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』には民話を紹介しており、『名田庄のむかしばなし』『日本の昔話一 若狭の昔話』に下記のような話が載っています。
「狐の玉」(おおい町名田庄西谷)
あるお寺の小僧が、和尚に言われて、盆用の華を取りに山へ入った。山奥にシキビを採ったときに根元に不思議な毛玉があった。小僧はそれを大切にして、行李に入れ、和尚にも「誰が来ても何があっても開けてはなりません」といった。小僧は用事で寺を出たが、その後、お婆さんが来て「小僧がいつもお世話になってます。洗濯物が溜まっているから今日は洗濯物を取ってきてくれと小僧に頼まれまして」といい、和尚が「お母さんですか」というと「そうです」といって、「洗濯物が行李に入っているといったから行李を出してくれませんか」といった。それで和尚は行李をわたして婆さんは中身を取って帰って行った。和尚はそんなことも知らずにいる。小僧が帰ってきて玉がないことを知り和尚を問い詰め怒り、和尚も謝った。小僧は玉を取り返さないと気が済まないといって、山伏に稲荷明神の格好をして狐のところへ行き、「お前ら寺の小僧に玉を取られたそうだな。その大切なものを取られたなら仲間はずれにしてやる」といった。狐は「取られていません」といった。稲荷の格好をした小僧は「ならば、あるという証拠を見せて見ろ」といった。狐は「これが証拠です」といって玉を渡した。小僧はこれを奪って帰り、和尚に取り返してきたことを報告した。小僧は狐を化かした人間ということで知恵のある者として出世した。
採話:金田久璋
参考:『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』
その他に、名田庄とは違う話として。
「狐の宝珠の玉」(美浜町菅浜)
敦賀の西福寺にお利口な小僧がいた。松原で毎日のように人々が狐にだまされていたのでこれを退治できないかということで、揚げを袋に入れて待ち構えていると案の定狐が出てきてきた。揚げが取られようとしたところで袋のひもを引っ張り狐を捕えて尻尾にある宝珠をとってしまった。それである晩に小僧の母さんがきて「白虎の玉を拾ったらしいな、見せてくれ」と頼まれて、狐の仕業とは思ったがあまりに似すぎていたため見せてしまい取り返された。小僧はそれをまた取り返すため稲荷の神主に化けて、稲荷さんの前に言って、「お前この間宝珠を取られたそうだな」といい、狐は取られてないといった。それで「ならば見せてみろ」といい、尻尾をピンと伸ばして見せたときにまた奪ってしまった。狐はその後小僧のところへ行き、「もう悪いことはしないから宝珠を返してほしい。代わりにこの玉をあげます」といって、代わりの玉を置いていった。
参考:『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』
これらと似た話は神奈川県にもあって、こういった人間が狐をだまして狐の宝物を取ってしまい、狐がだまされたことを悟ってそれを取り返しにくる話、宝物の交換条件などの話を「八つ化け頭巾」という一つの系統の話なのだといいます。
ここまででわかるのは狐にとっての狐の玉は、
狐の玉がないと化けられないという力の源
ということです。
昔話の系統では、この狐の玉は狐にとっての生命線なのでしょう。
『あどうがたり』にこのような記述があります。
狐の霊力はその白い毛玉にあるとされ、玉を失うことは致命傷となった。『今昔物語集』巻第二十七には、玉をひとに奪われ神通力を失った古狐の報恩譚が出ている。その毛玉は「小さき柑子(かむじ、みかん)」ほどの白い玉だという。『鼠璞十種』には「一握り計りの毛のかたまりにて、核とおぼしきもの、小豆より小なるもの有りて、白き毛、又は赤き毛すきなく生ひ出たり」とある。狐火はその毛玉が発光するのだとされた。
引用:『あどうがたり』
狐火とはよく言いますが、あれも狐の玉が源になっているという考えのようです。
狐の玉とは奇妙なものではありますが、日本の昔話や物語で出てくる「化かす狐」「霊力を持った狐」にとっては必須アイテムであるという認識だったのかもしれません。
古典系
『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』で紹介されている、「新日本古典文学大系三七七『今昔物語集』」から「狐、託人被取玉乞返報恩語(きつね、ひとにつきてとられしたまをこひかへしておんをほうずること)第四十」が一部紹介されており、白い玉が登場し、動物報恩譚として取り上げています。
他にも、武士が狐の玉を取り上げ、後に狐が返還を熱心に頼んだところ返してあげたところ、その狐の案内で盗賊からの危機を避けることができたという話もあるといいます。
どちらも玉を取り上げる話しで、どちらかというと民話より古典で見る玉を取る伝説の方が、人間と狐の対話がなされているような気もしますが、それでもやはり人間優勢なのは変わらずです。
ただ、玉を取る伝説とは違う、「玉」が登場する話でかの有名な「玉藻の前」の話があります。
玉藻の前の場合、どうやら「かしら」「ひたい」に玉があったようで、それは「しろき玉」であり「夜ひる照す玉」だそうです。
『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』曰く、「狐の玉に他ならない」ということです。
さらに「信太妻」いわゆる「葛の葉」の伝説でも
水晶のごとくなる、輝く玉を取りだし、この玉を耳に当て、聞くときは、鳥獣の鳴く声、手に取るごとくに聞き知り、さまざま、奇特これ多し
引用:『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』から「信太妻」(東洋文庫二四三『説教節』)
ということで、鳥獣の声を聞き分ける奇特のある玉として書かれており「狐女房譚」があります。「信太の森霊験記 葛の葉姫」で我が子への母の形見としてその玉を枕元に残し去っていくという描写が書かれています。
こういった有名な伝説にも狐の玉が登場しています。
狐の玉の伝承伝説
ここでいう伝承伝説は昔話の騙し合いではなく、狐の玉を拾った人々の伝承ということになります。
『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』は2021.3発刊です。
美浜町和田
七十年ほど前に母が近くの畑で狐の玉を拾い、前栽の赤く塗装した小祠に安置して祀っている。
美浜町気山
何代か前の当主が田園で狐の玉を拾ってきて、前栽の小祠に安置。
美浜町野口
先々代が近くの山で雄と雌の狐の玉を拾った。城山稲荷に相談したところ、めったに拾えないものなので家で祀るように言われた。それから何かあるといい方向に進むようになり、大事にすると「家に幸せが向く」という。
美浜町日向1
先代の父が「オタマ」を広島から持ち帰ったと聞いているが詳細不明。
美浜町丹生阿弥陀寺
佐田のある方が浜辺の松の枝に毛玉がかかっているのを見つけ持ち帰った。その後七年ほどして丹生阿弥陀寺の大久保松堂師が明治天皇の御真影の前で朝読経をしていると「佐田の本間家で稲荷を祀っているが時々玉を揉んだり抓ったりするのでほとほと困っている。丹生に帰りたいのでお迎えに行け」と神のお告げがあった。自転車で向かうと、不思議にもその家の者が玄関に打ち水をし戸を開けて待っていた。聞くと昨夜稲荷が夢でかくかくしかじか「お迎えせよ」とのお告げがあったという。それ以降丹生稲荷として祀られる。
美浜町坂尻
母が一言主神社裏の畑で見つけて床の間に置いていた。すると夜遅くに戸を叩く音がして、呼ぶ声がした。「誰じゃー」というと「オナジャー(俺じゃ)」と答え、「狐の大事とするフクノタマ」を返してくれとせがんだ。翌朝元のところに返したという。
小浜市中井
名田庄久坂から購入したもの。
小浜市池河内
六十年ほど前に炭焼きをしていた父が山中で拾い、床の間に据えた桐の小祠のガラスケースの中に祀った。
美浜町日向2
ある雪の日、魚の商売に敦賀に行ったとき、道に毛玉が現れ道を示してくれた。それで無事に敦賀に着いた。後に夢で「白粉を入れて祀ってくれ」と言われ、狐のお玉さんといい、商売の神として伏見稲荷の札と共に今も白粉を入れて祀ってある。
参考:『若狭路の民話 福井県三方郡編』
大野市八町(越前)
お稲荷さんのみたま
むかし話し手のおばあさんが玄関に立っていたら犬のようなものが横切ったので、何かと思ってウマヤの横のクラダナを見たら、むしろの上に白い玉が二つのっていたのだそう。それでおばあさんは家に持って帰って神棚にお祀りしたが、あるとき八町に廻ってきたお坊さんに見てもらったら「天照大神様の横は苦しいから外へ出さんとあかん」といわれ、外にお堂を立ててお稲荷様をみたまとしてお祀りしている。
白い二つの玉は夫婦だという。形は白狐のしっぽのような、綿のような、フワフワしたもので、丸くて、コロコロしていて、中にはかたい芯があり今も少しも色は変わらないのだという。
参考:『奥越前の昔ばなし』
大野市森政地頭方(越前)
尾んぼの玉
地頭方の某宅の屋敷にある稲荷の由来について。
その宅の方のおじいさんのまだ若かったころ、狐の尾んぼの玉が現れた。不思議なことと思い、木本の光徳寺さんでお経をあげてもらい、これを桐の箱に納めて厚く祀った。
お稲荷さんは機嫌のよいときはお供え物の食べ物を全部食べ、機嫌の悪いときはちっとも食べないということである。
参考:『奥越前の昔ばなし』
織田禅興寺地蔵堂(越前)
白狐の玉
上野区には、禅興寺通りという道がある。今は両側に家が建ち並んでいるが、むかしは、家がなく、さみしい通りであった。
この通りのはずれに、禅興寺があり、まわりには大きな杉の木や竹林があって、昼でも暗く、気味の悪いところであった。
村の人は、このお寺の道を通らなければ畑へいくことができなかった。
むかしから、このお寺の山奥には、大きな白狐が住んでいるという。まっ白い、それはそれは美しい白狐であった。夕方、お寺の鐘がなるころ、この狐が山から出て来て、畑にいる人をばかして、山の中へつれ帰るといううわさが伝わっていた。
この白狐は、人が住んでいる家の近くまで出て来て鳴いていたそうだ。そして、しっぽには、わたぼうしのようなまっ白い玉がついていた。
ある日、この玉が突然、しっぽから落ちたが、その玉を村の人が拾って家にもって帰った。よく見ると、その玉は、生き物のように動いていた。
むかしから、この白狐の玉を持っている者や、さわった者は、ばかになってしまうと言われていた。この話を知っていた家の人は、こわくなって、お寺の横にある小さなお地蔵さまのお堂の中に、お経をあげておさめたから何もなくてすんだという。
今も、そのお堂の中には、白狐の玉があって、ぐんぐん白い毛が伸びているだろうと言われているが、気味悪がって、だれもたしかめた人はいないそうである。
引用:『織田町民話編集委員会編 織田のむかし話』
越前にもある狐の玉
若狭が中心になっている狐の玉伝説ですが、越前にもあるということが今回郷土資料を漁ってわかりました。
しかも形状も毛玉で、または狐のしっぽの玉ともされていることが一致しています。
大野の方では祀られているので、狐の玉信仰としては若狭と同じと言えるでしょう。
地域が違っても県内で同じような形で伝わっている話があるということです。
ただ織田の話は若狭とは違い、奇妙で恐れられる存在だったようです。これが若狭の狐の玉との明確な違いですね。
狐の玉の採取の話
今まで見てきた通り、伝承のなかにある狐の玉の採取祭祀伝承は、
- 何十年も前に畑や山、道、敷地内で見つけて祀ったもの
- 他地域から購入、またはもらい受けたもの
- 夢のお告げや深夜の訪問者が来て、委託した又は返したもの
の三つのパターンに大きく分けられるようです。
『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』なかにはさらにリアルな話が語られています。
『伏見稲荷大社『朱』第二十三号掲載』の桑田忠親さんの話だそうです。
明治四十一二年、当時六、七歳のころ帰宅途中に、姉の足元に毛玉が飛んできて姉と取り合いになった。玉と言うより毛の塊で握ると変に温かく芯があった。易者に鑑定してもらうと「この白い毛の玉は、千年も経た白狐のしっぽの先についている玉であって、これを落としたが最期、その白狐は神通力を失い、やがて死んでしまう、とのことであった」玉を拾った者は、粗末に扱ったり紛失したりすれば不幸になり、大事にしまっておけば一生幸福でいられるという。
参考:『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』
形状も全く同じで、大野の狐の玉にあったように、やはり玉には芯があるようです。
これで狐の玉のだいたいの触り心地が想像できるような気がします。
信仰される狐の玉
一部伝承伝説の反復になる部分がありますが、信仰の部分をここに記します。
美浜町和田
玉と共に稲荷大社の御札が納められ、普段は榊を立てて水を供える。
美浜町気山
玉と共に、稲荷大社の大麻と神符、鏡がある。しだいに、世話が大変になり、不敬になるといけないとして、十数年前に麻生の城山稲荷にお祓いをしてもらい、神符などを伏見稲荷にお返しした。
美浜町野口
伏見稲荷の御札が納めてあり、祠の中は開けた事がない。氏神祭、彌美神社祭礼などに朝ご飯を神仏と共に供える。初午には揚げ、赤飯、御神酒を供える。祠周辺には「メンドイモノ(下着など)」を干すなと言い、犬を飼ってはいけないとする。玉は巾着に入れてあり、玉が動くともいう。
美浜町日向1
白粉をふりかけ、真綿で包んだ狐の玉を鉄の箱に安置。右に「正一稲荷大神璽」。普段は白ご飯、初午には赤飯、御神酒を供え、商売繁盛と家内安全を祈る。
美浜町丹生阿弥陀寺
白粉を敷いた皿の上に乗せ、「丹生稲荷」として、祀られている。時々、白粉をまぶすと狐の玉は、まるで生き物のように銀色の毛を波立たせるという。
阿弥陀寺は現在阿弥陀山龍渓院と合併して、狐の玉は龍渓院に移されたそうです。
美浜町坂尻
狐の福の玉は狐のしっぽについているもので、見ているとほわほわと白い毛が動く。神棚に供えるとよいことがあるというので供えておく。
小浜市中井
かつては土蔵の二回の遺影のそばの神棚に安置。今は台所の神棚。正月に御神酒、鏡、榊、氏神の三社神社の秋まつりには御神酒、赤飯を供え榊を立てる。神棚の中に若狭塗と思われる蒔絵の小箱が布に包まれて納められ、白粉を敷いた箱の中に大小の「白狐の玉」があり、灰白色の玉の中心は少し黒みがかる。当家は浄土真宗。長らく披見が禁じられ、党首も二、三回しか見ていない。
隣の家にもあり、白、灰、黄の三色があり、紙の箱に白粉を敷いて保存し、他見すれば霊力が失われるとされ、商売繁盛家内安全を祈る。
小浜市池河内
曹洞宗。床の間に据えた桐の小祠のガラスケースの中に白粉を敷いて祀っているが、現在粉々に形が崩れている。「運が向く」といって毎日拝んでいた。
おおい町岡田
「きつねの玉」といい、桐箱に納められ、床に置かれている。粉白粉が餌といい、蓋を取ると堆い白粉の上にふんわりと載ったきつねの玉。きつね色の柔らかいふわふわした毛の玉。十厘か、もしやそれに余ったかも知れぬ丈。母は祖母から頼まれていたらしくクラブ粉白粉を土産に持参した。/「不思議やでよ。白粉が減るやでよ」などと祖母が蓋を取りながら話す。竹藪から拾ってきた老爺から譲ってもらったと言っていたような気がする。皆が欲しがり羨まれているとも言っていた。祖母からは「勝手に見てはならぬ」。と言われていたが、私は訪ねるたびそっと床の間へ行き、きつねの玉を撫でるのを秘かな楽しみにしていた。手にとって悉と観察もした。揉んでみると少し固い芯があるかに思われた。子供心にもそれは生あるものとは思われず、白粉が減るのは圧せられているのであろうと想像したりもした。(後略)(『若狭の記録』1998-99、北国図書、1999)
引用:『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』
美浜町日向2
商売の神様として、伏見稲荷の御札と共に白粉。
大野市八町(越前)
白い二つの玉は夫婦だという。形は白狐のしっぽのような、綿のような、フワフワしたもので、丸くて、コロコロしていて、中にはかたい芯があり今も少しも色は変わらないのだという。
参考:『奥越前の昔ばなし』
大野市森政地頭方(越前)
木本の光徳寺さんでお経をあげてもらい、これを桐の箱に納めて厚く祀った。
お稲荷さんは機嫌のよいときはお供え物の食べ物を全部食べ、機嫌の悪いときはちっとも食べないということである。
参考:『奥越前の昔ばなし』
織田禅興寺地蔵堂(越前)
(前略)お寺の横にある小さなお地蔵さまのお堂の中に、お経をあげておさめたから何もなくてすんだという。
今も、そのお堂の中には、白狐の玉があって、ぐんぐん白い毛が伸びているだろうと言われているが、気味悪がって、だれもたしかめた人はいないそうである。
引用:『織田町民話編集委員会編 織田のむかし話』
禅興寺さんには、私がいつもお世話になっている武生龍泉寺さん伝いで、この狐の玉について尋ねましたが、狐の玉の伝承は伝わっていないとのことでした。
こちらはお寺に伝わっているというよりかは、民間で地蔵堂に祀った形になっているのでしょう。
その他
美浜町菅浜、若狭町上吉田、福井市脇三ヶ(浄土真宗最勝寺)にも狐の玉を拾った話があるが、神棚や仏壇蔵の中にしまい、その後新築などで行方不明の事例がある。
狐憑きなどの関連性が指摘されている
狐憑き、又は、狐持ち。それはうまく使えば幸運をもたらし、その裏には畏怖の念があり、反動で不幸が来ることもある。又は、丁寧に扱えば幸運を、粗末に扱ったり捨ててしまえばば不運が降りかかるというもの。
具体的には狐持になってうまくいけば金持ちになれるが、粗末に扱ったりすれば狐持になる前よりも貧乏になるというもの。
狐の玉の狐憑きにおいては、滋賀県で毛玉を祀っている家があったとしていますが、
桐の箱に入れて土蔵の守り神にしていた。金運がついてくると言われていたが、何かにつけて祈祷師を呼び座敷で護摩祈祷をしなければならず、会食にも費用が掛かり、コンコンサンを粗末に扱うと火事になるともされていたため、祈祷師に任せて現在は祀っていない。何かにつけて面倒なため、亡父からは決して拾ってきてはいけないと言われていた。
引用:『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』から滋賀民俗学会の『民俗文化』第三六三号(平成五年(1993)十二月二十五日)所載の粕淵宏明「『狐の毛玉』についてー坂田郡近江町」
狐の玉は自分で拾うものではありますが、ザシキワラシも憑き物として関連するものにあげられますし、狐関連でいえば、管狐もその類に入るのでしょう。論文の中では飯綱信仰も指摘されています。ただし福井県にはおおい町ごく一部でしか信仰されていないそうです。
『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』では、そういった狐持の金持ちの家が憑き物の反動で貧乏になる言い伝えは、庶民の妬みの感情から来ているものとみるとも書かれています。金持ちが貧乏になるという言い伝えが一つの嫉妬を晴らす先になっているとのことです。
ただし、『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』で特に調査された若狭の狐の玉では、特段「病的な狐憑き」は見られず好印象でとらえられていることが多いといいます。
しかし先ほども書いた通り、越前町織田の話では「民俗学的な狐憑き」というより完全な憑き物扱いされているので、ここが同じ福井県と言えども違いのある部分になっています。
狐の玉の流行
一時期、狐の玉が流行神となった時期があるようです。
『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』に紹介されている『鼠璞十種』には、「文化の季年に、狐の玉といふものはやりて」と書かれており、『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』にはその補足として、
狐の玉を図像化した宝珠は呪力を秘めた中世以来の神学的なシンボルとなっている。江戸時代の文化年間における、詐欺事件を伴った狐の玉による流行神の横行は一時の宗教現象にほかならない。
引用:『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』
としています。
民話や地域の民間信仰以外にも狐の玉が流行した時期があったのですね。
詐欺事件もあったとのことでそれほど多くの「狐の玉」と称した物が出回ったようです。
曹洞宗との関係
私は狐の玉を漁っている当初、狐の玉が祀られている美浜の阿弥陀寺(現在は阿弥陀山龍渓院)、織田の禅興寺とがあり、曹洞宗に関係があるのではないかと思いました。
武生龍泉寺さんでも稲荷を祀っています。
そこで武生の龍泉寺さんにお話を聞くとやはり曹洞宗と稲荷信仰というのはかなり結びつきが強いとのことです。
有名な豊川稲荷はその最高峰でしょう。稲荷信仰と曹洞宗が結びついた形態と言えます。
さらに、若狭の曹洞宗の割合もかなりの多さで、若さに狐の玉信仰がこれだけ盛んなのも、曹洞宗が何か関わっているのではないかと推測せずにはいられません。
しかし、今回の見てきた論文では福井市脇三ヶの浄土真宗最勝寺などにも話が伝わるとしていて、曹洞宗のみに伝わっているというわけではないということがわかりました。
私の思い違いだったのか、それともいい線まで行ったのか。素人目線ではそれもわかりません。
現在郷土史で確認できた福井県内の狐の玉伝承の地
- 美浜町和田
- 美浜町気山
- 美浜町野口
- 美浜町日向1
- 美浜町丹生阿弥陀寺
- 美浜町坂尻
- 美浜町菅浜
- 小浜市中井
- 小浜市池河内
- おおい町岡田
- おおい町名田庄久坂
- おおい町名田庄西谷
- 美浜町日向2
- 大野市八町(越前)
- 大野市森政地頭方(越前)
- 織田禅興寺地蔵堂(越前)
- 若狭町上吉田
- 福井市脇三ヶ(浄土真宗最勝寺)
- 敦賀市晴明神社
敦賀晴明神社の件は、毛玉とは違いそうなので、後に見て行きます。
一応は福井県内を網羅しているように思えます。若狭、丹南、奥越、福井平野部すべてで狐の玉が伝わっているようです。
共通する謎
- 生き物であるかのような毛玉
- 白い粉をふりかける
- 中に芯がある
狐の玉(毛玉)の奇妙な部分の共通点は大きくこの二つがあると個人的に思います。
むしころれが信仰するうえでの大きな魅力になっているのではないでしょうか。
毛玉が動くとか、白粉や供物を食べるといった話もこういう奇妙な伝承や風習から来ていると思います。
さて、その中でも白粉についてですが、『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』のなかで、このような指摘もされていました。
時折、毛玉に白粉を振りかけるのは変化の女性性を意識している証左である。
引用:『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』
それはつまり狐=女性的であるというイメージからなのか、日本にある様々な狐女の伝説のイメージなのか。それともフワフワとしたその柔らかい見た目からなのか。単純に変化するということが女性像と重なるのか。
いずれにしても「白粉(おしろい)」であることには変わらず、しかもこうも多く共通するということで、その風習は面白いものです。
また、狐の玉には中に芯があるというのも特異な点です。玉になっていればそれは確かに中に核があるのは当然と言えば当然ですが、こうも色々な場所で「芯があり~」と書かれていると、やはり共通する重要なワードになってきています。
『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』に紹介されている、先ほども『あどうがたり』で出たように、『鼠璞十種』には、毛玉の様子として
其のさま、一握り計りの毛のかたまりにて、核とおぼしきもの、小豆より小さなもの有りて、白き毛又は赤き毛すきなく生ひ出たり
引用:『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』から『鼠璞十種』
とあります。
それは生き物のようで、奇妙な存在として広い地域で共通の存在し信仰されてきているのです。
漫画で登場する狐の玉「東方project」
狐の玉は昔話にとどまらず、現代の漫画でも登場するようです。
東方projectという有名なジャンルがあります。東方projectはいわば同人系のゲームを原作とした幅広い作品になりますが、その東方projectの漫画版、東方茨歌仙6巻に「狐の玉」が登場します。
そこでは妖力のうまく使えない未熟な狐のサポート道具として説明されています。
ケサランパサラン
狐の玉によく似たものにケサランパサランというものがあるといいます。
その見た目も毛玉で、これもまた幸運を呼ぶというものです。
ケサランパサランの正体もおそらく野獣が捕食し排便した未消化の小動物の毛玉に他ならない。
引用:『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』
と記されており、その補足として、
姫路市立動物園の説明には「江戸時代より伝わる縁起物。正体は謎に秘められていて、これを見るとよいことがある と言われている 姫路市立動物園では ワシやタカ、フクロウなどの猛禽類のエサがケサランパサラン毛玉になるという説が有力である 信じるか信じないかはあなた次第」ということが書かれているようです。
ちなみに先ほど少し話した東方projectの漫画にもケサランパサランが関連づけられて紹介されています。現代の漫画だけあって良くできていますね。
『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』の論文を書いた金田久璋さんですが、一番最初に言ったように『あどうがたり』もこの方が書いています。
『あどうがたり』にもケサランパサランが出てきており、そこでは
狐の宝珠は「ケサランパサラン」ともいうそうで云々
引用:『あどうがたり』
と書かれており、完全に同一のものという認識で書かれています。
狐の毛玉とは何なのか
狐の玉は伝説では尻尾の毛玉であるということが言われていますが、ケサランパサランでは排せつ物であるとの説がありました。
『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』にも喜田貞吉主筆『民族と歴史』第八巻第一号「憑物研究号」(日本学術普及会、1922年)の宇那木玄光「美作地方の狐持と狐憑」の「狐持」の一説として、
其の玉と云ふのは、何処が初め(口)だとも、何処が終わり(尻)だとも分からない、まん円の白い毛の玉だと云います。(私の想ひますには、白兎などが猛鳥或いは猛獣に食べられた皮の丸くなったものだと思ひます。)
引用:『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』
と書かれており、やはり狐持の民俗学研究でも排せつ物という説が上げられているようです。
芯があるという話がたびたび出て来ていますが、その芯というのは毛が圧せられたものか、あるいは皮が圧せられたものかのどちらかなのでしょうか。
というわけで、狐の玉とは、
- 狐のしっぽの毛玉とする説
- 肉食動物の未消化の排せつ物説
の二つの説があるのですね。
狐のしっぽの毛玉である場合は狐の毛玉ということになりそうですが、肉食動物の排せつ物であるという場合は、狐の毛玉でもなければ、たとえ狐から排泄されたものであっても小動物の毛の塊であるという可能性も出てくるということです。
なかなか現実的にあり得そうな話になってきてしまいました。
敦賀晴明神社の白狐玉
排せつ物説とは裏腹に、そもそも毛玉ではないのではないかと思われる狐の玉もあります。
敦賀の晴明神社に「白狐玉」と称する玉が宝物として『敦賀郡神社誌』に書かれています。
宝物 白狐玉 一、箱入 古来よりの伝来と云ふ。
引用:『敦賀郡神社誌』
尊良親王、新田義貞の南北朝時代の話として、平山善久の隠匿の話の中に
土中ヨリ晴明三神ノ宸筆保食ノ神像白狐ノ玉石ノ下ニアリ是ニ仍テ此石聞及祈念石ト推尊シ(略)
引用:『敦賀郡神社誌』
という記述が見えます。
つまり、今の祈念石の下から白狐玉が出てきたということになるようです。
土の中から白狐の玉。毛玉かどうかは書かれていません。ただ、土の中にあったということは、これは今まで見てきた毛玉ではなく、石の玉ということになるのでしょうか。信太妻で登場したような玉だったのでしょうか。それとも箱の中に入っていた毛玉だったのでしょうか。
詳細は不明ですが、狐の玉が流行った江戸時代より前であるということと、土の中家から出てきた大昔の玉として今に「玉」として伝わるということは、朽ちない「石」の可能性が高いと思われます。
ただし昭和20年の敦賀空襲で行方不明になった可能性があります。
敦賀晴明神社へ取材に行き、その白狐玉について伺いましたが、残念ながらそういったものは伝わっていないとのことでした。
謎のままです。
狐の玉とは何なのか
さてここまで見て来て、狐の玉とはいったい何なのか。
その存在は大きく四つに分けられそうです。
- 毛玉
- 古典や伝承伝説上の妖力・霊力の塊
- 稲荷の狐の宝珠
- 石と推測されるもの
以上が今まで見てきた中の狐の玉の種類となります。
民俗信仰の毛玉。
物語上の毛玉や霊力の塊。
稲荷信仰上の宝珠。
特異な石と思われる存在。
一言に狐の玉と言えども、やはり長い間言い伝えられてきただけあって、様々な形であらわされています。
それだけ人を引き付けた存在であるということなのでしょう。
ご当地キャラに受け継がれる狐の玉伝承「キツネ玉 知りませんか?」
狐の玉は民話や信仰、漫画以外にも現代に受け継がれています。
狐の玉信仰が盛んな福井県にあってふさわしいキャラクターであり、狐の玉の昔話の後日談の形で存在している敦賀のご当地キャラ「キツネ玉 知りませんか?」さんです。
実は私が狐の玉に興味を持ったのもこのご当地キャラが始まりでした。
X(旧ツイッター)にアカウントがあります。日常のことがつぶやかれています。
https://x.com/princess_kohsin
物語が読めるのはnoteです。
noteには狐の玉の昔話から成る始まりの物語の章。昔話の後日談からなる物語の章。現代の敦賀の章。と大きく三部にわかれています。
狐の玉や敦賀の歴史とうまく絡まって物語が進行しており、更にそれが現在進行形で物語が続いているというキャラクターなので結構入り込めます。
敦賀のイベントにも参加しているので出会えることもあるかもしれません。
ぜひ見てみてください。
https://note.com/kitsunedama_note/magazines
狐の玉の伝承が続いてゆく
狐の玉は、その見た目もさることながら、昔話から伝承伝説から信仰まで中々に奇妙なほど魅力のあるものなのでしょう。
見た目はフワフワし、現代のグッズにも似たような見た目で親しみやすく、その割に奇妙な興味を引く見た目で。
昔話では子供にも聞かせやすいような話になっており。
伝承伝説では狐の伝説やご利益に似た分類の話になっており。
信仰では稲荷信仰と民間信仰で、しかも幸福をもたらすという対象になっている。
民俗学者も興味を引かれるこの存在は、おそらく今後も、この存在を知った人々を魅了し引き込んでいくのでしょう。
そして現代、未来まで続く物語となってゆきます。
参考文献
金田久璋『狐の玉と宝珠の図像学的考察 -若狭の屋敷稲荷の口承と象徴化 伏見稲荷大社『朱』第六十四号抜刷』2021.3
『あどうがたり』
『若狭路の民話 福井県三方郡編』
『奥越前の昔ばなし』
『織田町民話編集委員会編 織田のむかし話』
『敦賀郡神社誌』
WEBサイト『民話の部屋』
『東方茨歌仙』6巻
『キツネ玉 知りませんか?』





コメント