福井県小浜市に小浜城があります。そこにはかつて人柱が立てられたという伝説があり、今でもその人柱の地蔵が城に祀られています。
今回は城跡、天守、石垣と共に、人柱伝説そして組屋六郎左衛門と組屋家について探っていきます。
組屋地蔵と人柱の伝説
組屋地蔵と人柱の伝説は『組屋地蔵尊由来記』を参考にいろいろなところで載せられていますが、ここでは2つ載せます。
慶長六年(1601)、若狭の領主となった京極高次は、これまでの後瀬山城から下竹原の地へ城を移すことにしました。
これは大変な大事業で、まず下竹原村に住んでいる漁師の人たちを現在の西津へ移転させることから始まり、海や沼を埋めて工事は進められました。
このため、若狭中の人たちが、その工事に使われました。
このお城をつくるために年貢が高くなるなど、領民は大変苦しめられることになりました。
お城の工事は、海のすぐ近くでしたので、ずいぶんむずかしく、石垣は築いてもくずれ、築いてもくずれして、中々工事は進みません。
「人柱をたてて、お城の永久安全をはかってはどうだろうか」
と、相談が決まり、小浜の一番の大商人、組屋六郎左衛門に「人柱」を差し出すよう命じました。
これを請けた組屋六郎左衛門はあちこちとたずね、人柱になる娘を探しましたが誰ひとり請けてくれるものはなく、困っていました。
このことを知った組屋六郎左衛門の娘は、父が困っているのを見かねて、自分が「人柱」になることを承知しました。
それから幾年月がたちました。小浜のお城は美しく出来上がり、若狭の海にその姿を浮かべていました。
人々は、このような痛ましい、かなしい「人柱」となって死んでいった娘のことを、いつの間にか忘れ去っておりました。
お城の殿さまも、京極家から、酒井家へと変わりました。
酒井の殿さまは忠勝公は、徳川幕府の大老職という重要な仕事をしていたので、小浜のお城には城代家老として三浦帯刀を置き、若狭の国を治めさせていました。
あるとき、家老三浦帯刀が城中を見回っておりますと、番の役人が五、六人寄り集まってヒソヒソと話をしています。家老は何気なくその話を聞きました。
「蜘蛛手櫓の近くで、夜ふけになると女のしのび泣く声がする」
「なんとも不思議なので、あたりを見ても人影もないし、気味悪くて、ゾーッとする」
「蜘蛛手櫓の見回りは、もうこりごりだ」
などと、話しています。
これをきかれた家老は、家来をつかわされて、京極家が小浜城をを築く時のもようを調べました。
築城の時、組屋の娘が「人柱」になっていたが、その後供養がなされていないことがわかりました。
家老はこのことを聞かれて
「それは憐れなことをしたものだ」
といって、お地蔵さまをつくられ、蜘蛛手櫓近くにお祀りして「組屋地蔵」となづけ、小浜城のお守りとされました。
このことがあってから、蜘蛛手櫓の女の泣き声がきかれなくなりました。
引用:『ふるさとの昔話』
この地蔵は、むかし小浜城本丸のくもてやぐらのそばに祭られていたが、いつのまにか、忘れられていた。
ところが昭和三十四年七月小浜城趾の石垣を修理した時、地下1.8メートルのところから地蔵さんが発見された。現在この地蔵さんは、小浜城趾石垣のそばの小さな堂の中に祭られている。
慶長六年(1601)領主京極高次は、後瀬山にあった城を海のそばへ移すことにした。
この時に城が長く残るように、人柱を立ててはとの意見が出た。このことを、京極高次の家来が、当時小浜の町老役で豪商の組屋六郎左衛門に相談した。六郎左衛門は、あれこれと思案したが、人の子を人柱にすすめることもならず、やむなく自分の娘を差し出すことにした。娘は父の心境を察して、父のいうとおり人柱となった。
その後京極高次は、国がえとなり、寛永十一年(1634)酒井忠勝が若狭国の新城主となった。
酒井忠勝は、幕府大老の職にあったため、江戸にいなければならなかったので、城代家老に若狭の政治をまかせていた。その城代家老は、三浦帯刀であった。
帯刀が、ある夜一人で城内を見回っていると、城の本丸の近くで城番の武士が五、六人集まり、ひそひそと話していた。「くもてやぐらの近くへ行くと、毎夜女のしのび泣く声が聞こえる。あたりに人影もなく、きつねかたぬきが、たぶらかすのだろうか。」といっている。
三浦帯刀は、武士たちに気づかれるようわが家へ帰り、召使を呼び、ひそかに町へ出て、城の昔のことを聞き出してくるようにと命じた。召使は、町家を回り尋ねると、京極さまの築城の時、人柱になった組屋の娘の話をした老人があった。
これを聞いた三浦帯刀は、使いの人を石工のところへ出して、一体の地蔵尊を刻ませた。帯刀は地蔵尊を城内に安置し、お坊さんをまねき、人柱になった組屋の娘の供養を行った。これよりこの地蔵を組屋地蔵と呼んで、小浜城の守護とした。
これから女の泣く声もなく、いつしか忘れられていたが、寛文二年(1662)の大地震の時、城が大損害を受け、くもてやぐらをはじめ本丸から二の丸にかけて、石垣が崩れおちた。その復旧工事の際、昔のことに気づかなかった役人や人夫が、組屋地蔵を埋め込んでしまったのである。
引用:『越前若狭の伝説』より『組屋地蔵尊由来記』
昭和三十四年に発見されたということが理由だからか、いつも私が『越前若狭の伝説』と共に見ている昭和11年発刊の『福井県の伝説』には、この組屋地蔵のことは載っていませんでした。
ちなみに『蛛の網:若狭の文化と伝統(若狭郷土叢書;第1輯)』には、「昭和三十四年の修理」という表現ではなく、「昭和二十四年九月の風水害再び石垣が崩れた際に地蔵尊を発見し、宮司香川政男氏が有志の喜捨を得て三十四年に祀った」としており、修理の理由まで書かれているのでした。
- 人柱が起こったのは慶長六年(1601)あたり。
- 供養がなされた(地蔵が作られた)のは寛永十一年(1634)以降。
- 寛文二年(1662)に一度紛失し。
- 昭和三十四年に再度祀られた。
それにしても人柱をたてた段階で供養がなされていなかったとは、なんとも悲しいことです。
人柱の組屋地蔵

組屋地蔵は現代にも伝わっています。しっかりと説明板もついています。
組屋地蔵があるのは小浜城正面道路を向かって左へ進むと、小浜城に隣接した隅の方に安置されています。この組屋地蔵の斜め後ろにあるのが蜘手櫓です。人柱となった娘が泣いていたという櫓跡です。

一見、小浜でよく見る地蔵さんと思ってしまいますが、隣にはしっかりと組屋地蔵の由緒が書かれています。今はこうして安置され、きれいな花も手向けられて供養されています。
組屋六郎左衛門と組屋という家について
組屋といういえばどんな家なのでしょうか。
小浜で組屋と言えば、疱瘡の神の御札でも有名で、以前当サイトでも取り上げたことがありました。
この時も、組屋六郎左衛門が出て来ていました。
果たしてこれが同一人物なのか、はたまた屋号が一緒なだけで別人なのか。
しかし、疱瘡の神の出来事は永禄年中(1560ごろ)だとされています。組屋地蔵の慶長六年(1601)と時代は近しいです。ただ、だとしても40年ほどは期間が空いています。なかなか微妙なところです。
しかも『小浜のみなと:一名・遠敷の栞 増訂2版』には、安政年間(1855年~1860年)の大火を機に用水を引く際に協議協力した中に組屋六郎左衛門が出て来ています。またほかの資料にはほとんどの年代、文書に組屋六郎左衛門の名が出て来ており、『小浜市史 通史編 下巻』には、明治三十年にも組屋六郎左衛門が出て来ています。これは名前を引き継いでいるようです。
『蛛の網:若狭の文化と伝統(若狭郷土叢書;第1輯)』にはこうも書かれています。
小浜町上流の子弟で漢学を学ぶものは全て組屋六郎左衛門に就いたといわれ
引用:『蛛の網:若狭の文化と伝統(若狭郷土叢書;第1輯)』
さらには、『蛛の網:若狭の文化と伝統(若狭郷土叢書;第1輯)』には系図まで載っており、一部見てみると「組屋六郎左衛門宗悦」「組屋六郎左衛門正隆」「組屋六郎左衛門信重」などがいるのです。
なので疱瘡の神の組屋六郎左衛門と人柱の組屋六郎左衛門が必ずしも一緒とは限らないわけですね。
かつて組屋鯤溟仁山二翁という人物がいたようです。
その人物について、『小浜のみなと:一名・遠敷の栞 増訂2版』では、
組屋家は小浜町最古の門閥にして祖先は楠氏の支族に出つと云ふ
引用:『小浜のみなと:一名・遠敷の栞 増訂2版』
としています。
先ほど見た通り、組屋六郎左衛門はどうやら名を受け継いでいるようなので、この組屋鯤溟仁山二翁の組屋家が同じであるかどうかはわからない。と言いそうになりますが、『蛛の網:若狭の文化と伝統(若狭郷土叢書;第1輯)』を見てみると組屋鯤溟仁山二翁に関連付けられて組屋の系図が書かれているので、同じ家ということになると思います。
またそれと同じようなことも組屋六郎左衛門の項目で『蛛の網:若狭の文化と伝統(若狭郷土叢書;第1輯)』にかかれており、
組屋六郎左衛門
組屋家は楠木氏の支族で、その祖は楠木正成の弟正季の後裔といわれている。小浜市では最も古い門閥家で元偶屋と称し代々市税を掌る。丹羽氏以来代々の国主から町役である公用銭を免ぜられていた。国主が入国の時は先ず此家に入るのが例となっていた。
引用:『蛛の網:若狭の文化と伝統(若狭郷土叢書;第1輯)』
また、武将ともかかわりがあったようで。
若狭塗は小浜の素封家組屋六郎左衛門が天正年間織田信長公に献上した若狭塗盆が公のお気に入りとなり、それ以来若狭国の名産として盛んになり
引用:『若狭小浜の今昔物語 改訂』
若狭塗を有名にしたのも組屋六郎左衛門であったというのです。
『蛛の網:若狭の文化と伝統(若狭郷土叢書;第1輯)』によると、文書『組屋宗円言上書』を見ると、武田元明が死んだ天正十年頃に組屋家と豊臣家・京極家と特別な関係が生じたとしており、その縁あって慶長五年に京極が小浜に来たときは、縁の深い組屋を頼ってきたのだという考察がなされています。
国主すら頼ってきて、国に入る時にはまずこの家に入るという、小浜で最も強い力を持った家だったことが伺えます。
どうやら組屋家は『小浜市史 通史編 上巻』によると、戦国時代初期の時点ですでに小浜の商業を取り仕切っていた存在だったようで、「初期豪商」とされています。
豊臣時代から海外貿易も取り仕切っていたようで、またこうも書かれています。
組屋が当時小浜の町奉行と町年寄りを兼ねるような地位にいたことを窺わせる。さらに組屋は、戦国時代以来領主の年貢を請負っており、江戸時代にはいっても領内の村々の代官となりその収納に当たっており、領内支配の一端も担っていた。
このように初期豪商としての組屋は、領主権力と強く結びつきながら、海運・商業・貿易・年貢の請負などに従事することで富を蓄えていった。
引用:『小浜市史 通史編 上巻』
そんな組屋六郎左衛門は先ほど書いた通り近代までその名をとどろかせています。
森田貯蓄銀行も組屋六郎左衛門の宅を借りて支店を開店したといいます。
長い時代の中で豪商として小浜を取り仕切っていた存在だったようです。
京極氏と酒井氏との二つの城主下で伝わる人柱
京極氏
京極氏は組屋を頼ったとしていますし、組屋とも仲が良かったのであるということが先ほどの記述を見ればわかりますが、そういった深い仲も仇となる時があるということのようです。
人間関係は希薄な方がいいということなのでしょうか。それとも大きすぎる家だったからでしょうか。
大きな影響力を持ち、殿さまにもひいきにされていた組屋家。そんな組屋家を襲った人柱という悲劇。
違う見方をすると、組屋を良く思っていなかった町の者たちは必ずいたと思います。そういった者たちから見ると、この組屋の人柱の悲劇はかなりおいしいものだったでしょう。
年貢も高くなったというので、時代背景を照らし合わせるならば、組屋家が年貢の請負もしていたということなので、そこから妬みに加えて、組屋への憎しみもあったのかもしれません。
妬ましい、憎らしい相手の悲劇を作り上げることで、自分たちの心を慰めていた、組屋をよく思わない人たちの間で広まった話なのかもしれません。
もちろん、年代や人柱が立ちられた場所などが伝わっているだけに、ただのうわさ話というわけでもないのでしょうが。
いずれにしても、こういう時に犠牲になるのは、物事を決める家の主人などではなく、物事によって決められた、運命に翻弄される娘である場合が多いので、なかなか可哀想なものです。
しかも伝説を見る限りでは、特段お堂や供養もされていなさそうなので何とも哀れなことです。
酒井氏
まだまだ殺伐としていた京極氏の時代から少し社会も穏やかになってきて、人々の心にも余裕が生まれてきた頃。そして組屋の人柱の伝説も忘れ去られていった頃。
人柱という存在は哀れであるという認識もされてきて、私の考察を付け加えるなら、組屋への妬みから広まった人柱という話も忘れ去られて、組屋に対する妬みも和らいできたのか。(それでも権力は健在だったようですが)
そういえば、あんなことがあったなぁというような認識で一部の老人たちに人柱伝説が伝わっていた時代。
三浦帯刀が人柱を哀れと思ったその心には感心します。それとも城内の噂を鎮める為に行ったことなのかもしれません。いずれにしてもここで初めて人柱を供養したということで、それは素晴らしいことだったのでしょう。
そして結局一旦はまた忘れ去られてしまいました。
小浜城
小浜城と神社

まず小浜城を見る前に見ておきたいのが、小浜場付近にかかっていた橋です。こちらは現在工事がなされ新しい橋に架け替えられているようです。結構長い工事です。欄干が一部木でできている古めかしい橋となっていました。

バス停がありましたが、現在このバスが通っているかは不明です。

神社の鳥居が見えてきます。小浜場内にある小浜神社です。


神社も立派です。
石垣の数々

西櫓跡。石垣の積み方には詳しくないので、何積みというのかはわかりませんが、大きな石を積み、その間に小さな石を挟んでいる積み方です。打込接ぎというのでしょうか。わかりません。でも見ごたえがあります。

住宅地はすぐそこです。

小天守。
こちらの積み方は違います。洪水で再建したことが関係あるのでしょうか。

緩やかな階段もあります。そしてここは蜘蛛手櫓。人柱になった娘が泣いていた場所です。
階段は至る所にあります。そして何より巨木が多い。若狭らしい巨木です。生命力に満ち溢れている杜のようになっています。
天守

天守への道は史跡巡り欲を掻き立てる様子です。そして写真を撮っていても鳩はお構いなしに小石をついばんでいます。




どうでしょうこの感じ。とても史跡らしい。
どうしてこれが有名にならないのか。どうしてこの小浜城をもっと前面に押し出さないのか。私は不思議でなりません。もっと人気になっても良いものだと思います。少なくとも私は城跡としてとても魅力を感じます。

それはきっとこの小浜城にいる人柱がこの素晴らしい城を城跡になって以降も、今までずっと守ってきたからなのでしょうか。
ずっと守ってきてくれたのなら、今小浜城を日本中に知らせて、存在を認知させてほしい。それがある意味での一つの供養という形にもなるかもしれません。
立派な城の遺構と、もう忘れてはいけない伝説
城の遺構は美しいもので、昭和に修復されたといっても築城当時の様子を見ることが出来ます。
本丸も見ごたえがあって、なかなか面白い場所です。
この小浜城はあまり小浜の観光で押し出されているところを見たことがありません。もっと前面に出してPRしても良い場所なのではないでしょうか。少なくとも私はそう思いました。
そして、哀れな組屋の人柱。
運命に翻弄された娘。しかも二度も忘れ去られてしまった過去。
この組屋地蔵の伝説も人柱伝説だからと控えめになっていないで、もう二度と、いえ、三度と忘れてはならないと、多くの人の心へ深く刻み込む必要があるのではないでしょうか。
参考文献
『ふるさとの昔話』著者小浜市連合婦人会ふるさとづくり特別委員会 出版1974.3
『越前若狭の伝説』著者杉原丈夫 出版1970
『蛛の網:若狭の文化と伝統(若狭郷土叢書;第1輯)』著者赤見貞 出版1971
『小浜のみなと:一名・遠敷の栞 増訂2版』著者江口成徳 出版明治41.9
『小浜市史 通史編 下巻』著者小浜市史編纂委員会 出版1998.3
『若狭小浜の今昔物語 改訂』著者木村確太郎 出版1981.6
『小浜市史 通史編 上巻』著者小浜市史編纂委員会 出版1992.3
関連記事:『福井県の人柱伝説まとめ』
基本情報(アクセス)
| 最寄り駅 | JR小浜線小浜駅から徒歩19分 |
| 自動車 | 小浜ICから5分 |
| 駐車場 | 2台分ほどあり |


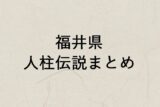


コメント