福井県大野市の富田、阪谷地区には周辺の山が噴火や山体崩壊を起こして飛んできたとされる巨岩巨石が散乱しています。
今回取り上げる釣鐘岩もその一つです。経ヶ岳の噴火によって散らばった大岩はいくつもあり、有名なのは山伏岩です。釣鐘岩はそれと同類の巨岩になります。
伝説
釣鐘岩
塚原神社の東の田の中に、釣鐘の形をした岩があります。
白山火山の噴火の時に落ちてきたのだといわれて肌がいぼいぼになっているし、形が釣鐘そっくりなところから釣鐘岩というらしいです。この岩に耳をあてて、じっと聞いていると、中から竜宮の乙姫様が茶わんを洗う音がするということです。
引用:『とみたの民話』
蕨生区から塚原区にかけて、経ヶ岳が大噴火したときに飛んで来たと言われる七つの大きな岩がありました。昭和36年からの塚原土地改良工事で破壊された物もありますが、現在は、山伏岩、釣鐘岩が残されています。
釣鐘岩
釣鐘の形をした岩は竜宮城に繋がっており、耳を当て、じっと聞いていると、中から竜宮の乙姫様が茶碗をを洗う音がするということです。
引用:『とみたのお宝マップ』
https://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/chiikidukuri/kouminkan/tomita-k/otakara.files/otakara-ura.pdf
郷土資料では白山の噴火となっていましたが、最新の公式では経ヶ岳の噴火ということになっているようです。実際周辺の大岩伝説は、経ヶ岳の噴火ということになっており、この釣鐘岩も経ヶ岳の可能性の方が高いと思われます。
竜宮の乙姫伝説については同じ語りがされているため、この部分がメインの伝説ということになりそうです。
岩から聞こえる音というのは結構いろいろなところで耳にします。
同じ大野市内で、これまた大岩の伝説で「女郎岩」という、中から機を織る音が聞こえるという伝説が伝わっているところもあります。
また、乙姫伝説もよく耳にします。
巨岩にはなにか、女神的存在が宿っている、または女神が住んでいる、岩そのものが女神など、女の人や女の神様に関わるものが多いように感じます。
また、川や海なら竜宮を連想できますが、陸地の巌から竜宮を連想するというのもなかなか興味をそそられます。
どういった経緯なのか。私は民俗学者ではないので、伝説を集めて紹介することしかできませんが、この謎が不可彫りされる日を楽しみにしています。
地理
釣鐘岩があるのは、塚原という地域です。
国道158号線近くにあるので、自動車でならアクセスは良好です。
釣鐘岩は伝説の通り田の中にぽつんと島のようになってあります。土地改良後も残していただいたことに感謝です。
現地へ赴く

釣鐘岩の北側の農道を歩いて行くと、釣鐘岩への道が続いています。畦道のような道です。
釣鐘岩本体までは少し小丘とまで言わない程度登ります。草が生い茂り、虫も多いので、虫よけは必要かと思います。

ほんの少し登ると、説明版があります。こちらでも伝説を知ることができるので、現地でその話を復習することもできます。
そしてこちらが釣鐘岩です。

思った以上に尖っています。
そして草が生い茂りすぎて、岩に耳を当てることもできそうにありません。マダニいると嫌ですし。
溶岩性の岩なんだなということはわかります。大野でよく見る大岩の類と同じ質感です。
残された釣鐘岩
こういった大岩が昔は七つあって、それはまさに里の風景だったのでしょう。
田が整備され、道が整備されると同時に、そういった里の風景は消えていきますが、それもまた時代の流れ。
その中でもこうして残されていくものもあるのです。そしてそれは本にも記され、今後もし何かあっても、記録されていくのでしょう。
ただ正直な気持ちを言うと、今残っている釣鐘岩や山伏岩は、今後も残していってほしいし、地域を見守る自然信仰の神として、そこにあり続けてほしいです。
参考文献
『とみたの民話』著者富田公民館 出版1984.10
『とみたのお宝マップ』
基本情報(アクセス)
| 最寄り駅 | 越美北線越前田野駅から徒歩25分 |
| 自動車 | 荒島ICから4分 |
| 駐車場 | なし |


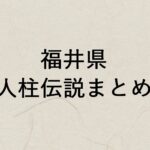

コメント