福井県永平寺町旧松岡町に比丘尼塚という人柱伝説があります。それは結城秀康時代に本多富正が主導で九頭竜川岸に築いた元覚堤関係の伝説で、この堤を作る際に何度も崩れたため人柱を立てなのだといいます。
藤島地区中ノ郷との境界付近にあったもので、今回はその伝説と現地の様子をここに書き記します。
人柱伝説
比丘尼塚(中ノ郷)
中ノ郷地籍の九頭竜川の堤防はこの川が氾濫すると切れて萬人の迷惑は一通りではなかった。名にし負う九頭竜川のことであるから其の度にどうしたら堤防が切れないようになるだろうかと思案に余った村人は或る年の治水工事に占をたてた。其の翌日のことである工事場のところを一人の尼さんが通りかかった。村人は占者の言った通りにいやがるこの尼さんを捕えて人柱として生埋めにすることにした。尼さんは所詮逃れることは出来ないと覚悟をきめて、「私も出家の身です萬人の悩をすくうことが出来るなら喜んで其の犠牲となりましょう」と遂に埋められたのであった。それからは年毎の大水に堤も切れなくなったという。その後幾度かここの堤は改修されたが松岡町と中ノ郷地籍の間の堤防には比丘尼塚だけは昔のままに取り残されている。
引用:『福井県の伝説』
また出ました、占い。
こういった占いをする人が人柱をたてよというのは何度か見たことがあります。いったいどういうつもりなんですかね!と憤ったところで、きっと昔はそれが許されたのでしょう。
元覚堤
芝原用水は、志比境で九頭竜川から分かれ、川に沿うて走る。用水と川の間の堤を元覚堤という。松平秀康のころ、本多丹波守(伊豆守富正)が名を受けてこの堤を築いた。彼の法名を元覚というので、この堤を元覚堤と名付けた。
むかしこの堤は、出水ごとにくずれた。よって旅の尼僧を捕え、生きながら人柱として築きこめたところ、その後くずれることはない。このあたりに比丘尼塚(びくにづか)がある。
(越前国郡県細志)
注
比丘尼塚は、松岡町と旧東藤島村中の郷との境にあり、東藤島村誌では中の郷地籍のこととしているが、ここでは越前国名蹟考および吉田郡誌に従い、松岡町に入れておく。
引用:『越前若狭の伝説』
中ノ郷地籍のこの堤防に「比丘尼塚」と呼ばれているところがあるが、この塚は、昔この堤防が構築される際に、ここを通りかかった比丘尼が「女の身でも人柱となって、私もこの堤防をお守りいたしましょう」と、人柱になるべく生き埋めにしてもらった所だと、伝えられている所である。これは伝説であるから真偽の程はわからないが、近年まで堤防の傍に塚の形が残っていた。
引用:『東藤島村誌』
人柱を立てた状況がどうも郷土史によって違います。
- 元覚堤が大水のたびに崩れるため人柱をたてた。
- 元覚堤の構築の際に人柱をたてた。
細かいですが、この二通りがあります。
また、『福井県の伝説』では、
「いやがるこの尼さんを捕えて人柱として生埋めにすることにした。尼さんは所詮逃れることは出来ないと覚悟をきめて、「私も出家の身です萬人の悩をすくうことが出来るなら喜んで其の犠牲となりましょう」と遂に埋められたのであった。」と、もうほぼ無理やり強制的にならされたという感じでした。
しかし地元郷土史の『東藤島村誌』には「いやがる」とか「逃れることは出来ない」とか言う部分はなく、尼僧が自ら人柱になると志願したような形になっています。
さてここは深堀して良い所なのかどうなのか悩みますね。
比丘尼塚(中ノ郷にあり、昔時水難除に、之を埋めたりとか、)
P431
比丘尼塚
細志云、昔、此堤、出水毎に崩損す、終に、旅人の尼僧を捕へ、生なから築籠しかは、其後崩るる事なし。
P436~P437
引用:『吉田郡誌』
『越前若狭の伝説』『吉田郡誌』、そして後で見ますが、『新訂越前国名蹟考』は「尼僧を埋めたということがあった」ということしか書いていません。
それが強制だったのか志願だったのか。
まあ、こういう何かの犠牲になる時って大体、強制・半強制な事が多いですよね。でもそう思っていると、本当は志願だった時に、その人に失礼であるということになりますし。ここら辺はあまり深堀しないほうが良いですね。
いずれにしても少々郷土史によって状況が異なるようです。
元覚堤とは
さて少し見ましたが、そもそも元覚堤(げんかくてい)とはいったいどういうものなのか。
元覚堤の説明を郷土資料から見ます。
比丘尼塚の記述も併せて書いてあることが多いので、この二つはセットになります。
元覚堤
〇此間九頭竜川の南縁の堤なり。国初本多丹波守法名元覚築かれしにや。此辺比丘尼塚と云つか有。俗説あり。〇昔此提出水毎ニ崩損ス。終旅人ノ尼僧ヲ捕ヘ生ナカラ築籠シカハ、其後崩ルル事ナシト云。細志
引用:『新訂越前国名蹟考』
九頭竜川は、本村の北境を流れ、芝原用水は、下志比境にて、九頭竜川より分れ、九頭竜川に沿うて流る。其間に元覚堤あり、〔名蹟考〕云国初、本多丹波守、本名元覚(伊豆守富正上篇用水の條参看)命を奉じて、築かれしにや、此辺、比丘尼塚と云うつかありて俗説あり。
九頭竜川改修の為め、此堤は本(四十二)年三月、改築されしも、比丘尼塚は、取残されたり、此堤は、九頭竜川左岸、築堤の起点にして堤上の両側には櫻樹を植えたれば、数年後には一層の風致を添うなるべし。
引用:『吉田郡誌』
伝説のところで書いてありましたが、「元覚」というのは本多丹波守の法名ということで、この名がつけられたということです。
もう少し細かく見ていきます。
慶長六年五月家康の次子結城秀康が越前に入国以来、その藩老本多富正(府中武生城主三万九千石)及び、今村盛次(丸岡城主二万五千五十石)は、藩政の根本施策の一つとして、格別に治水に意を注ぎ、久しくかへりみられなかった堤防の修築について、太きな力を尽くした。
ことに富正は、北ノ庄城下(福井)を水害より守るためには、福井地方の東北を限る松岡より中ノ郷、北野、大和田、舟橋間の九頭竜川左岸に、大堤防を構築しなければならぬとして、築堤に力めたので、それ以来本村は、その余恵を蒙って、永く水害より解放されるところとなった。人々はこの事蹟を景仰して、彼の号並びに法名元覚にちなんで、中ノ郷付近の堤防を「元覚堤(げんかくてい)」と呼ぶ様になったと伝えられている。
当時九頭竜川は、松岡の下流地点より、島橋を経て原目の山際に出で、吉野川に合流する分流があった。分水地は、分水のために堤防が切れている上に、本川が右に曲流する点に当たっていたので、少しの出水にも迸流が打ち当り、極めて決潰しやすい状態にあたったので、富正は、この地点の構築については、分流を制約するとともに、格別の努力を払った。この地は比丘尼塚と呼ばれているが、伝説によれば比丘尼を人柱として堤を築いたと伝えられている。この伝説は越前国名蹟考などにも載せられているところを見ると、余程古くから語り伝えられている話の様である。
元覚堤は、本村を竜質の惨より守り、住民をして永く生業に安んぜしめてくれた恩顧深い堤防である。この堤防の構築について大きな力を尽くしてくれた本多富正こそは、まさに本村の大恩人であると云わねばならぬ。
引用:『東藤島村誌』
松岡町の室地籍より、本村の中ノ郷、北野上の地籍へかけての九頭竜川の堤防を昔から「元覚堤」と呼ばれている。この堤防は慶長年間の頃に福井城(当時は北ノ庄城と云った)が築城された際に、時の国老、本多富正公(府中城主)が、福井城下を水害より護る目的を以て構築したもので、「元覚堤」とは、富正の号、「元覚斉」及び法名「元覚」にちなんで呼んだものである。
本村は、この堤防の余恵を蒙って、水禍より護られ、ながく生業に安んずることが出来たのである。
引用:『東藤島村誌』
というわけで、人柱が起こったのは、もし堤建設の時に起こったのだとしたら、慶長六年(1601)ごろということになります。ただもし、何度も決壊した後に人柱をたてたというのであれば、慶長六年以降のいつなのかは不明です。
比丘尼塚はいまに伝わる
さて、この比丘尼塚。今も残っているのでしょうか。
サムネイルでネタバレしていますが…。
というわけで探してみます。
といっても、郷土史内でこのように記されていますね。
- 「ここの堤は改修されたが松岡町と中ノ郷地籍の間の堤防には比丘尼塚だけは昔のままに取り残されている。」
・・・『福井県の伝説』著者河合千秋 出版昭11 - 「近年まで堤防の傍に塚の形が残っていた。」
・・・『東藤島村誌』著者東藤島村史編纂所 出版1956.9
ということは、昔は残っていたが、今は無くなってしまったということなのでしょうか。
そう思って、ネットで昔の地図の一部を見ることのできる、『時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」』を探してみると、たしかに「比丘尼塚」という地名が書かれているのです。
そしてそれは1909年の地図には書かれていますが、1930年の地図からは消え、さらに平成になるとその場所に建物が建っているのです。
その建物とは、「福井県内水面総合センター」です。
比丘尼塚があった場所、そこに立っているのです。
これは無くなってしまったか…。
場所は特定できたので、半ばあきらめて、私は現地へ向かいました。


福井県内水面総合センターの入り口から奥の方が少し丘らしきものになっています。きっとこのあたりに比丘尼塚の塚が築かれていたのだろうなという感じです。
そしてこの奥の公園があります。遊具は使えなくなっています。私はそこで見つけました。見つけたのです。
堤防からの見るとわかりやすいです。堤防に上がります。

一角。なんか立ってますね。説明板が立ってますね!

あるのです。あったのです。もう福井県内水面総合センターができてなくなったかと思われていた、比丘尼塚。あるんです。見つけたときのあの感覚、たまらんです。

今もこうして残されているのです。人目にはつかないかもしれません。しかしこうして残されているのです。これに価値があります。よかった。本当によかった。
この比丘尼塚。松岡なのか藤島なのかどっちなのか、という問題がありますが、古い郷土史『新訂越前国名蹟考』や郷土史をまとめた『越前若狭の伝説』に松岡の地籍として書かれており、なおかつ『ふるさと中藤島百年誌』には、
比丘尼塚について
比丘尼塚の伝説が語られているが、その所在が不充分なため調査の処、松岡観音町の北裏に当たる処に小高い山のようなものがあり比丘を人柱にして水害をなくした伝説の内容は事実であるが、松岡地籍であり当地区とは関係がないことが判明したので除去することとする。
引用:『ふるさと中藤島百年誌』
と書かれていたため、本サイトでも松岡=現永平寺町として載せることとしました。
またこの文献について、「伝説の内容は事実であるが」と言い切ってしまっていることに衝撃を受けました。
この伝説は単なる伝説ではなく、事実に近い伝説という認識でいたほうが良いようです。
だからこそこうして残されていること、私は嬉しく思います。


堤防は歩道になっています。
このあたりが元覚堤なのでしょう。

九頭竜川が見えます。暴れ川です。
ここに人柱が立てられ、それが今もしっかりと伝わっている。そのことを忘れないようにしなければ。
人柱の伝説を残すということ
たとえ、人柱の塚跡に新たな建物や公園を作ろうとも、人柱伝説というある意味で暗い伝説をなかったことにはせず、現地でこうして伝え続けているということに私は尊敬を覚えます。
そして人柱になった尼僧は、どんな気持ちで人柱になったのか。無理やりなのか、すすんでなのか。いずれにしてもその伝説は伝え続けるべきであり、忘れ去られるべきではない伝説なのです。
覚えていることがきっと供養になるはずです。
参考文献
『福井県の伝説』著者河合千秋 出版昭11
『越前若狭の伝説』著者杉原丈夫 出版1970
『東藤島村誌』著者東藤島村史編纂所 出版1956.9
『吉田郡誌』出版1909
『新訂越前国名蹟考』著者井上翼章 出版1980.10
『ふるさと中藤島百年誌』著者中藤島百年誌編集委員会 出版1975.3
時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」
関連記事:『福井県の人柱伝説まとめ』
基本情報(アクセス)
| 最寄り駅 | えちぜん鉄道観音町駅から徒歩10分 |
| 自動車 | 福井北ICから5分 |
| 駐車場 | 福井県内水面総合センター |

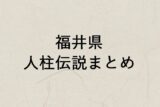


コメント